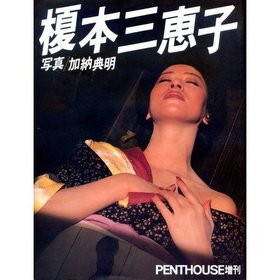“想像を絶するほど汚い” 17世紀ヴェルサイユ宮殿の衛生事情
ルイ14世が1682年に王室をヴェルサイユ宮殿に移転して以来、この場所は単なる狩猟用の小屋から、王の権威を象徴する壮麗な宮殿へと変貌を遂げたのである。しかし、華やかな宮廷生活の裏には、想像を絶する不衛生な現実が隠されていたのだ―――。
衛生に対する当時の認識
■入浴をめぐる誤解
17世紀の人々にとって、入浴は健康を脅かす危険な行為と考えられていた。歴史家ジュール・ハーパーによれば、温水は体を弱め、毛穴を広げて病気を招くと信じられていた。その結果、人々は長湯を避け、簡単な清拭を好んだ。
驚くべきことに、「太陽王」ルイ14世自身、生涯でたったの2回しか入浴しなかったとされる。しかし、彼が全く清潔さに無頓着だったわけではない。毎朝、タオルで体を拭き、香水とアルコールで体を擦り、手を洗うなどの清潔習慣を持っていたという。
■トイレ事情の悲惨さ
当時のトイレ事情は現代人の想像を絶するものであった。個人用の便器(チャンバーポット=おまる)は存在したが、公共のトイレは常にあふれ、汚水は壁や床を伝って隣接する部屋に流れ込んでいた。最初の水洗トイレが宮殿に登場したのはルイ14世の後継者ルイ15世の時代、1738年のことである。
興味深いことに、王自身がしばしば客人を迎えながら用を足すという、現代では考えられない習慣があった。プライバシーの概念が現在とは全く異なっていたのである。
■悪臭との戦い
宮殿内の悪臭は筆舌に尽くしがたいものだった。目撃者の証言によれば、通路、中庭、廊下は尿や糞便で満ちており、その悪臭は常軌を逸していた。
貴族たちは大量の香水で悪臭を隠そうとしたが、皮肉なことに、それはさらに状況を悪化させるだけであった。歴史家アラン・コバンは、「過剰な香水の使用は、自分自身と周囲の空気を浄化する手段」だったと述べている。
■排泄の公然性
プライバシーという概念はほとんど存在せず、公然の場所で排泄することは珍しくなかった。窓から無造作に排泄物を捨てる習慣もあり、通行人は落下する汚物に注意を払わなければならなかった。
当時の証言によれば、ある貴族女性は公然と排泄を行い、他の証言では、ギャラリーに立つ人々が隅々で排泄を行っていたという。ルイ14世は最終的に、使用人に週一回の清掃を命じるほどであった。
■身だしなみと衛生
貴族たちは清潔な下着を重視し、ルイ14世は汗をかけば単にシャツを替えるだけであった。一日に何度もシャツを変えることは、富と地位を示す手段でもあった。
■歯と虫歯
精製された砂糖の登場により、貴族の歯は急速に腐敗していった。ルイ14世自身、晩年には歯を失っていた。しかし、それでも口腔衛生は美的理想の重要な要素とされ、様々な粉末や洗口液が使用されていた。
■シラミと対策
当時の流行であったカツラは、シラミの巣窟と化していた。男性は頭を剃ることでシラミ対策を行ったが、女性はそうはいかなかったようだ。
■食品衛生の問題
下水道の問題は食品衛生にも大きな影響を与えた。ある記録によれば、汚水がマリー・アントワネットの個人的な厨房に流れ込み、すべてを汚染したという。腸内寄生虫は日常的な問題であり、ルイ14世自身も6インチもの長さの回虫を排出したとされている。
■宮殿を徘徊する猫たち
ヴェルサイユ宮殿には、家畜や野良猫が数多く存在していた。宮廷の住人たちが飼育する家猫もいれば、残飯に引き寄せられた野良猫も多数いたのである。
これらの猫の存在は、衛生状態をさらに悪化させる要因となった。猫の糞は宮殿の敷地中に散らばっており、状況は極めて不衛生であった。さらに悲惨なことに、死んだ猫の死骸が町の目抜き通りにまで放置されているような状況だった。
猫の繁殖は、宮殿内のネズミ対策という側面もあったが、同時に新たな衛生上の問題を引き起こしていたのである。宮殿の住人たちにとって、これらの猫は厄介者であると同時に、ある種の必要悪でもあったといえるだろう。
■色彩と衛生のユーモラス
この不潔な環境は、皮肉にも新しい流行色を生み出した。「ノミ色(プース)」や「皇太子の糞色(カカ・ドーファン)」といった独特な色名が宮廷で生まれたのである。
ヴェルサイユ宮殿は、その輝かしい外観とは裏腹に、衛生面では悲惨な状況にあった。それは単なる不潔さではなく、当時の社会構造、科学的知識、そして文化的規範を反映する、興味深い歴史の一側面なのである。
現代の私たちからすれば信じられない衛生環境であるが、これらの事実は当時の人々の日常生活を生き生きと描き出している。歴史は時に、私たちの想像を超える驚きに満ちている。
参考:Ranker、ほか