中学部活の“ヒップホップ禁止令”が呼んだ波紋。「些細な問題すら当事者間で解決できない」社会が示すもの
◆“ヒップホップ禁止令”が話題に
東京都千代田区立・麹町中学校の“ヒップホップ禁止令”が波紋を呼んでいます。6月12日配信の朝日新聞デジタルが詳しく報じています。
昨年の段階で学校側が今後体育祭でのヒップホップダンスの発表の場を設けない旨を通知。つづいて秋の文化祭での発表もなし、さらに今年4月からは部活動の内容も「創作ダンス」にするなどの変更を立て続けに決定しました。ショックを受けた部員の保護者46人が、5月下旬に教育委員会に抗議文書を提出する事態に発展しているのです。
校長は、中学生がヒップホップダンスを踊ることに様々な意見があったこと、そしてダンス部が運動部であることから、日本中学校体育連盟の大会を目指すべく創作ダンスに変更したと答えています。そのうえで「ヒップホップは部活でなくてもいいと思う。方針を変更するつもりはない」と、決定の正当性を説明していました。
ところが、事態は収束するどころか、ついには5月21日の国会で国民民主党の伊藤孝恵議員が盛山正仁文科相に関連質問をするまでの騒動に発展しました。国会で議論すべきほどの題材でないのは、火を見るより明らかです。
すると、問題はそこに至るまでの間に、学校と生徒、保護者サイドでまっとうな議論の場を持てなかったことにあるのではないでしょうか? 双方の立場から考えたいと思います。
◆問題は「ルールを変更すること」ではない
まずは学校サイド。朝日新聞が伝えているように、ヒップホップダンスが禁止されたきっかけは、学校長の交代です。生徒の自主性を重んじていた工藤勇一前校長が退任してから、制服や担任制度のあり方など、様々な点が見直されたといいます。ヒップホップダンスもその一環なのでしょう。
もちろん、こうした変更自体が悪いのではありません。トップが変われば組織も変わる。けれども、その変化が劇的であり大きければ大きいほどに、時間をかけて詳細に説明する必要があります。生徒の生活を左右するのですから当然です。
今回で言えば、部活動に関わる制度の問題であると言ったところで、生徒の納得が得られないのも仕方ない。そもそもヒップホップダンスは文部科学省の指導要領に記載されているのですから、それを校内から追放するかのような対応には相応の説明が求められます。日本中学校体育連盟うんぬんでは、根拠として弱すぎる。
つまり、生徒の納得を得るためには、学校長以前に一人の大人としてフェアに向き合う必要があったということなのです。“私はヒップホップというものをこう見る。だから中学教育にはふさわしくない。皆さんの気持ちはわかるし申し訳ないとも思うが、これは学校長としての見識、価値観である”ということを、正面切って言わなければならないのですね。
◆十分な説明をしなかったことが学校の落ち度
たとえば、ヒップホップには少なからず後ろ暗い側面がある。麻薬売買、銃撃戦に加えて、最近では人身売買の嫌疑をかけられているパフ・ダディや反ユダヤ主義を公然とかかげるカニエ・ウェストのような人たちも世間を騒がせている。
そういうダークサイドと無縁ではないカルチャーの、たとえうわべだとしても、格好を真似しているだけなのだから大丈夫というわけにはいかない。どうしてもやりたいのであれば、それは校舎の外でお願いしたい。これは私の教育方針に反するものである、とか。
校長先生がヒップホップやブラックミュージックについてどこまでご存知かはわかりませんが、制度の問題だけで終わらせずに、なぜヒップホップダンスを校内から締め出さなければいけないのかの自らの価値判断を正直に伝えるべきだったのですね。そうした考えが正しいか間違っているかではなく、価値観の押し付けと言われようが、まずは率直な考えを忌憚なく訴えることが子供を導く大人の責任だからです。
それとは逆に、臭いものに蓋をしようと処理すればするほど外に広がります。現に国会にまで取り上げられてしまいました。本来、この程度のことは学校内で処理できるはずだし、しなくてはならない。
多感な年頃の中学生に対して、あくまでも他人事の事務処理として終わらせようとした学校サイドが、初手から大きなミスを犯してしまったのです。
◆感情論に訴えた生徒・保護者サイドの問題
次に、生徒、保護者サイドの問題です。“ヒップホップを禁じられて泣く子もいた”といった感情論に訴えたことは悪手でした。なぜならば、こうした激しい情動に対して、世論は冷淡な客観性でバランスを取ろうとするものだからです。
いままで許されていたものが突然ダメになるなんておかしい、子供がかわいそうだ。その心情は理解できても、むしろ理解できるほどに、そうは言っても世の中にはやむを得ないこともあるよね、という合意形成がなされる。すると、校長先生の言う「ヒップホップは部活でなくてもいいと思う」を、過大に評価する土壌が出来上がってしまうのですね。
筆者もヒップホップが部活でなければいけないとは思いませんが、だからといって校長先生の説明が十分だとも思わない。
そこで部活にクローズアップすると学校制度の話で逃げられてしまうので、ここは「ヒップホップを踊ることに対し、さまざま意見があった」という“意見”とはどのようなものがあったのか、またそれに対する校長の見解を冷静に問いただしていくほうが効果的だったのではないかと思います。ヒップホップが目の敵にされた理由の言質を取るということですね。
校長の不勉強や考えの浅さが具体的に知れ渡れば、生徒や保護者を支持する人たちはもっと増えていたでしょう。
◆ある意味「社会の断絶」を示すニュースでもある
けれども、残念ながらこちらも教育委員会に訴えたことで親の手から離れてしまいました。学校と生徒、保護者の双方がディスコミュニケーションのまま、騒動だけが大きくなっている。
だからといって、これが切実な問題であるかと言われると答えに困ってしまう。にもかかわらず、各方面に飛び火している状況は滑稽に映ります。
麹町中のヒップホップ禁止令は、本来朝日新聞が取材する必要も、国会で質問される必要も、そしてSNSのおもちゃにされる必要もなかった些細な話です。
しかしながら、この程度のことすら当事者間で解決できなくなってしまった、巨大で底の深い社会の断絶を示すニュースでもあるのでしょう。
文/石黒隆之
【石黒隆之】
音楽批評の他、スポーツ、エンタメ、政治について執筆。『新潮』『ユリイカ』等に音楽評論を寄稿。『Number』等でスポーツ取材の経験もあり。Twitter: @TakayukiIshigu4





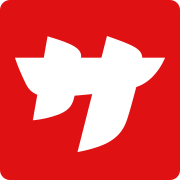









いち(
6/14 13:58
ヒップホップ風の創作ダンス踊ったらええやん。