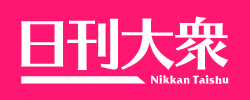永遠のプロレスラー「三沢光晴」友人が語る「最強エルボー」伝説
どれだけ月日が流れようとも、忘れられない“緑色の勇姿”。リングに人生を懸けて闘った足跡がここに!
2009年6月13日は、プロレスファンにとって忘れることのできない日だ。プロレスリング・ノアの広島大会。そのメインイベントで悲劇は起きた。
「トップレスラーの三沢光晴さんが、バックドロップで投げられた直後、リング上で動けなくなりました。異変を感じて試合を止めたレフェリーに、三沢さんは“ダメだ。動けない”と答えた後、意識を失い、帰らぬ人となりました。享年46という若さでした」(スポーツ紙プロレス担当記者)
多くのファンは、プロレスラー・三沢光晴がリングにいない喪失感を、長らく埋めることができなかった。
あれから12年。三沢さんが残した偉大な足跡は、今なお色褪せることはない。
「高校時代にアマレスで国体優勝を果たすなど活躍し、1981年にジャイアント馬場率いる全日本プロレスに入門しました。若手時代からセンス抜群で、馬場さんも目を細める“秘蔵っ子”でした」(前同)
84年から2代目タイガーマスクとして活躍していた三沢さんが自らマスクを脱いだのが、中心選手の天龍源一郎の離脱で、団体が揺れていた90年5月の東京体育館大会でのこと。ここから、必殺技のエルボーを武器に、団体を引っ張るエースへと急成長する。
同年6月、“怪物”ジャンボ鶴田を初めて破ると、8月に川田利明や小橋健太(現・建太)たちと「超世代軍」を結成。その後、「四天王プロレス」と称される、肉体の限界に挑戦するかのような激しいファイトを繰り広げ、多くのファンを熱狂させた。
元『週刊プロレス』全日本プロレス担当記者の市瀬英俊氏は、こう語る。
「三沢さんはプロレスラー的な“俺が俺が”という主張をしない選手でした。リングの闘いがすべてで、無駄なアピールをせず、試合の激しい攻防だけで観客を魅了する。そんな“言葉を必要としないプロレス”でトップを取ったレスラーが、三沢さんだったと思います」
市瀬氏は、97年1月、三沢さんが当時の三冠王者、小橋健太に挑んだ試合が忘れられないという。
「今も鮮明に覚えていますが、フィニッシュのランニング・エルボーを放つ直前、中腰状態の三沢さんがリング上で声にならない声で吠えたんです。ふだん、客席にアピールをしないレスラーでしたから、余計に驚いた。あの試合は“凄いもの”としか形容できない激闘でした。極限の中で出た、自然な感情の発露だったように思います」(前同)
この試合は、その後のプロレス史を変えたという。
「それまでは、遺恨やジェラシーなど、ドロドロした感情が闘いのベースでした。でも、三沢さんと小橋さんは志を同じくする同門同士。いがみ合っていなくても、あれだけ激しく、そして観客の心を揺り動かす試合ができると証明しました。今では、こうした遺恨抜きの試合は当たり前になりましたが、原型は、あの一戦にあったと思います」(同)
■下ネタの天才?
リング上では寡黙なイメージが強かった三沢さんだが、素顔は下ネタを愛する、気さくな人でもあった。フリーアナウンサーの徳光和夫の次男で、三沢さんと親交が深かったタレントの徳光正行氏は、「酒の席での下ネタトークは鉄板だった」と語る。
「三沢さんは、上野や錦糸町といった庶民的な街の飲み屋の常連でした。よくご一緒させてもらいましたが、サラッと口にするから下品に感じない。これも三沢さんの“得意技”の一つだと思います」
こうした下ネタはお互いの胸襟を開く、“人間関係の潤滑油”だったようだ。
「僕もさんざんイジられました。あれには参りましたが、三沢さんは、相手の特性をすぐに見抜いて笑い話に変える天才なんです」(前同)
命懸けで闘うリングでの雄姿と、飾らない素顔。その魅力は多くの女性ファンの心を奪った。2代目タイガーマスク時代に結婚し、公表もしていたが、特に超世代軍時代の女性人気は圧倒的だった。会場には女性ファンが詰めかけ、声をからして三沢さんを応援した。
「一度、三沢さんとファンのハワイツアーに同行取材しましたが、ツアー客26人の大半が女性。最終日、ホノルル空港でハワイに残る三沢さんとの別れを惜しむ女性が次々と泣き出し、収拾がつかなくなってしまった。三沢さんも困り切って、最後は不機嫌になっていました(笑)」(前出の市瀬氏)
また、義理堅く、仲間に愛され、後輩に慕われた。
「約束事は、相手が誰であれ、どんなに小さなことでも必ず守る。地位や肩書きでなく、人としてつきあう。だって、飲みの席で誘われたからって、区民体育館のママさんバレーに、ちゃんと参加するんです。そりゃ、女性にも男性にもモテますよね」(前出の徳光氏)
■ジャイアント馬場の逝去後、よく歌った曲
三沢さんは自身の性格について、市瀬氏のインタビューで、こう語っていた。
〈妥協したくないとか、途中であきらめたくないとか、簡単に言えばそういう俺がいるわけよ。(中略)「俺には関係ねえよ」って言えば終わるんだけどさ。「それじゃお前、悩んでいるヤツがかわいそうだろ」という自分とさ。あとから、あの時やってやればよかったな、と思いたくないんだよね。結局は、自己満足なんだけどさ〉(『週刊プロレス』97年7月15日号)
仲間が集まる飲み屋では、よくマイクを握り、昔のアニメや特撮ヒーローの曲を歌っていた。特に好きだったのが『ウルトラマンレオ』の主題歌だった。
「“誰かが立たねばならぬ時、誰かが行かねばならぬ時、今この平和をこわしちゃいけない、みんなの未来をこわしちゃいけない”という歌詞に、三沢さんの生き方というか、信念を感じました。馬場さんがお亡くなりになってから、この曲を歌う頻度がグッと上がったんです」(徳光氏)
99年1月31日、全日本プロレス社長であり、現役レスラーでもあったジャイアント馬場が61歳で突然、この世を去る。
全日本のエースだった三沢さんは、その3か月後、社長に就任。だが、わずか1年ほどで解任され、自ら辞表を提出すると、00年6月、プロレスリング・ノアの旗揚げを発表した。
JASRAC 出 2105072-101
■プロレスリング・ノアで“三沢改革”
「馬場夫人の元子さんとのたび重なる衝突が、一つの背景としてありました。三沢さんがファンのために何か試みようとしても、馬場さんが作った伝統を重視する元子さんは聞く耳を持たなかった。結局、25人以上のレスラーやスタッフが追随し、ノアに移りました」(前出のプロレス記者)
同年8月5日のノア旗揚げ戦では、レーザー光線やオーロラビジョン、花道の設置など、華やかな演出が目を引いた。それは全日本社長時代にできなかった“三沢改革”の一端だった。
「一方で、三沢さんは選手のために、巡業後のオフの日を増やしたり、引退後の仕事先を作ろうとしていた。また、選手や社員へのインフルエンザの予防接種や、定期健康診断を義務づけました。当時のプロレス団体としては画期的なこと。06年に小橋さんのがんが発見されたのも、この健康診断のおかげでした」(前同)
04年と05 年に東京ドームに進出。超満員の観衆を集め、ノアは「業界の盟主」といわれるまでになる。
「ただ、旗揚げから4年目くらいから、三沢さんのツラそう表情が目につくようになりました。社長兼レスラーですから、休む暇もほとんどなかったはず。猪木さんでいう新間寿さんのようなキレ者の参謀がいれば、その後を含め、心労を溜め込まずにすんだのかもしれませんが……」(徳光氏)
長きにわたる激闘の代償として、肉体は悲鳴を上げていた。特に首の状態は悪く、上を向くことも、後ろを振り返ることも、ままならなかったという。それでも、団体の長として、リングの内外で走り続けた。
「三沢さんは、いつも“信念を持たずに自由を得ることはできない”と語っていました。あの日から、13年になる今も、僕は、その言葉を大切にしています。自分が生きていくうえで、迷ったときは“三沢さんだったら、どうしているだろう”と考えるんです」(前同)
46年間の人生を全力で駆け抜けた、三沢光晴の生きざま。令和の時代となっても、語り継いでいきたい。