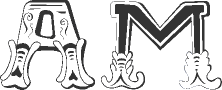「若さ」は一瞬で、希少なのか。何者かにならなくては…と焦る人へ/葭本未織
「20歳までに何者かにならなくてはいけない」
「若さ」とはいったい何なのかということを10年近く考えてきた。
17歳の夏休み、AKB48が大ブレイクした。田舎の女子高生だったわたしにまでその余波は届き、夢中になってメンバーの名前をひとりひとりおぼえた。
9月1日。久しぶりの登校で驚いた。同級生の数人がAKB48のオーディションを受けていたのだ。1次、2次と進み、惜しくも落選した彼女たちは、クラスメイトにあれやこれやとエピソードを語っている。
「すごい、自分で受けてみるなんて考えもしなかった。」
呆然としつつも感嘆し、それとともにひどく素直に、わたしは不思議に感じていた。
「どうして彼女たちはオーディションなんか受けたんだろう?だってわたしたちもう若くない。こんな歳だよ。アイドルなんてなれるわけないのに。」
あの頃、わたしは本気で自分のことを老婆だと思っていた。まだたったの17歳だったのに。
それから2年後、わたしが19歳の女子大生だったころ、大学院生の彼氏が言った。
「俺にはもう選択肢が無い。でも君は違う。若さがある。まだ何にでもなれる。」と。
今ふりかえると新卒で就職した友人たちと自分を比べていたのだろう。彼もまた本気で自分のことを老人だと思っていた。まだたったの23歳だったのに。
私はその言葉を真に受けた。
どうやらわたしにはまだ「若さ」があるらしい。しかし、20歳を過ぎたら、人は何者にもなれないようだ。ましてや大学を出たら、人生は余生。あとは真っ暗な坂道を転げ落ちていくだけ。だから20歳になるまでに、せめて大学を出るまでに、わたしは何者かにならなくてはいけない。
それから4年後、23歳のわたしは無事に「何者か」になった。東京に出て演劇を創り、劇作家として、憧れていた某賞に推薦された。女優として、夢みていた某ドラマのヒロインオーディションを受けた。……どちらも推薦されただけ、受験しただけなのに。だのにわたしは、それまでの道のりが長かったせいか、その道すがら、多くの夢破れた屍を見たせいか、必要以上に浮かれた。真夜中、誰もいない路上でこう叫びたかった。
「わたしはみんなが憧れてもできないことができる。わたしはみんなとちがう!」
生まれて初めて、自信が湧き上がってくるのを感じた。しかしこの自信は、優越感と言い換えることもできる。それは他者の賞賛によって裏打ちされたもので、けして自分自身の内部から湧き上がるものではかった。他人の評価に基づいた自信は、その後、わたし自自身をひどく脆弱なものにさせた。
当時、わたしが熱心に言われた賛辞こそ「君には若さがある」というものだった。
でもわたしの演劇作品はいわゆる若さ、つまり溌剌さを感じさせるものではない。むしろ静謐で、閉ざされた世界を垣間見るような作品だった。クライマックスには必ず憎悪の爆発のエネルギーがあった。
その作風に手ごたえを感じながらも、観客の感想の中に「葭本未織には若さがある」という賛辞には、答え合わせが当たった小学一年生のようにはしゃいだ。
あの頃わたしは、自分にはいいところなんて一つも無いと思っていた。そんな自己認識と、他者からの賞賛の中身がかけ離れていたからこそ、わたしはその言葉に固執した。
賞賛は蜜よりも甘い。他人の評価からかりそめの自信を手に入れて、なんとか生きている人間にとっては、それは甘さだけでなく、中毒性もある。
真夜中のエゴサーチで、わたしはなんとか呼吸する。わたしは他人の印象通りの人間になりたい。明るく、元気よく、くよくよせず。いつも笑っている人間になる。だから、もっともっと聞かせて。じゃないと、生きていけない。
一方、賛辞を聞けば聞くほど、わたしは不安定になった。なぜなら「若さ」というのはいずれ必ず失われるものだったからだ。
わたしが生き続ける限り、細胞は日々変化し、少しずつその数を減らしていく。若さというものは一瞬で、希少である。だからこそ人の心を打つのだ。しかし、だとしたら、生き続けるということは失うことでもある。わたしが努力し勝ち得たものが、ようやく形になりはじめたものが、少しずつ無くなっていくということだ。
わたしは恐ろしかった。日々進化ならぬ、日々劣化。そう言葉で茶化しながらも、心底怯えていた。その怯えは次第に心をむしばみ、早々に死んでしまったほうがいいのではないかと、一人、歩道橋から交差点を見つめることもあった。
行き交う車の群れを眺めていると、若いころの自分が、少し離れたところで見ているような気がした。わたしが17歳だったころ、若さとはわたしにはもう無いものだと思っていた。19歳だったころ、若さとはどうやら、無限に選択肢があることだと知った。23歳だったころ、若さとはどうやら、エネルギーのことを指すらしいとわかった。辞書を引くと、「若いこと」「活力に満ちていること」「未熟であること」と出てくる。
すばらしいことだ。でも、いずれわたしの手の中からこぼれ落ちていくものだ。
涙がつたって落ちた。こんなこと誰にも言えなかった。
わたしはまだまだ若い。だって今でもわたしはのめりこみやすい。
つい最近、小説の学校に通い始めた。ひとりで物を書くことへの限界を感じたのだ。競い合う仲間、切磋琢磨できる友人が欲しい。そう思い、まずは体験入学に行くことにした。電車に乗って、久しぶりの学校。おそるおそる入室した教室には、一人、制服を着た女の子がいた。講師からその子が書いたという小説を手渡され、何の気なしに目を落として、わたしは驚いた。
なんだ、この静謐な小説は! 若さと対極にありながら、若さそのもののような小説は!
湧き上がるこの印象が一体どこから生まれているのか、わたしは何度も何度も文字を目で追った。そして気がついた。書かれた言葉ひとつひとつに、それが選ばれた必然があるのだ。この言葉でなくてはいけない。そう筆者が感じ、選び取った言葉がつらなると、そこには完成された世界観が生まれる。そして必然は強い執着から成る。頑迷な思い込みが、言葉と言葉をつなぎ、エネルギーを生む。
その時、アッと声が出た。この言葉を、いつか、わたしも言われた。静謐さ、閉ざされた世界、そして若さ———。ようやくわかった。若さとは、「研ぎ澄まされた集中力がある」ということなのだ。
27歳も半ばを過ぎて知ったのは、人間は体の老化より先に、精神に変化が訪れるということだ。失恋してもさして引きずらないようになったり、今まで打ち込んでいたことを「やりきった」と辞めて、心機一転新しい仕事を始めたりする。執着や頑迷さが失われ、広い視野を持てるようになる。
つまり、のめりこむことが少なくなる。寝食を忘れるような没入感が持てなくなる。夢、目標、大好きだった人、愛していたもの。他には何にもいらないと、あんなにも夢中になっていたのに。
こうでなければいけない、という思い込みが無くなり、情熱が失われる。そこには解放感と、一抹の淋しさがある。だからこそ人は、向こう見ずなまでにまっすぐだったあの頃を思い出してこう言うのだ。
「若かった、すばらしかった」と。
ようやくわかった。あの時、わたしに「若さがある」と言ってくれた観客の真意が。わたしは言葉の一面に振り回されすぎていた。言葉には多義がある。そんな当たり前のことを忘れていた。
制服を着た女の子を見つめた。少女らしい頬のふくらみが輝いていた。彼女の小説には、明るさはない。溌剌さも、元気の良さもない。ただ、圧倒的な集中力がある。そしてそれをわたしは「若い」と感じている。
毎日をどれほど頑張っても、人間は老いてゆく。いずれ失われていく「若さ」があなたのすばらしさだと言われているような気がしていた時、何をしても、過去よりも未来が輝くことは無くて、生きることが恐ろしかった。だけど、わたしの肉体から少しずつ去りゆくものが「集中力」だとしたら、それは年齢を重ねることや肉体の衰えとは関係ない。
教えてくれてありがとう、と心の中でつぶやいた。
そして講師に言った、「わたし、入学します!」
*
人のいない電車に揺られ、家路をたどる。27歳を半分も過ぎた夏の始め。怯えは消え、自信だけが残った。わたしはまだまだ若い。だって今でもわたしはのめりこみやすい。失恋を引きずっているし、夢だって諦めきれていない。すぐに思い詰めて、死ぬだのなんだの騒ぎ立てる。頑迷で、向こう見ず。そして何より自分の集中力が、言葉を選ぶとき、他の何に対峙するときも際立って研ぎ澄まされる。その実感が、在る。これは誰かの評価に裏打ちされたものじゃない。わたし自身がそう感じてる。そう信じてる。だからわたしはまだまだ若い。そしてこれからも若い。きっと永遠に、若いのだ。
Text/葭本未織
初出:2020.07.23