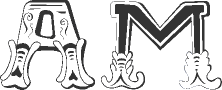わたしは痛みこそが≪愛すること≫だと勘違いしていた。はじめて眠れたあの春の日/葭本未織
窓を開けると勢いよく花びらが舞い込んだから、愛想のよいタクシー運転手が笑った。首都高速に降りしきる桜。眼下に流れる千鳥ヶ淵を眺めながら、「前に同じ光景を見たことがある」と、わたしは数年前の春の日を思い出した。
◇
その頃、わたしは上手く眠れなくて、夜というのは襲い来る≪恐怖≫と闘うための時間だった。その恐怖とはこうだ。
誰しにも、その人をその人たらしめている要素というのがある。例えば、女であること。地方の生まれであること。今は東京に一人で住んでいること。ご飯を食べるのが好きなこと。運動するのが嫌いなこと。長く眠らないと元気になれないこと。仕事が好きなこと。
このような一つ一つはさして特別じゃない要素が、無数に組み合わさることによって固有のわたしを創り出す。誰にでも当てはまるようなありきたりな要素が、複雑に絡み合い、集体となってわたしの世界をつくっている。 けれど目を閉じて眠っているあいだに、そうした≪わたしをわたしにさせるもの≫が突然失われたら?
ありえないとは言い切れない恐怖だった。当時は東日本大震災からたった数年しか経っていなかった。一瞬ですべてが変わってしまったあの光景を目の当たりにしてから、わたしにとって≪世界≫というのは不滅ではなく、すぐに壊れてしまう水晶細工なようなものになった。
宝物には、それを見張る門番が要る。壊れやすい世界がきちんと持続してゆくように、わたしは常に目を見開いていないといけない。わたしをわたしにさせるものが、何一つ、こぼれ落ちてゆかないように。
そう考えると夜は長い闘いの時間になり、わたしは一睡もできないまま朝を迎えた。そんな夜を何度も重ねたある日、銀色の車を持った男に出会った。
その男はどうにもピンとこない男だった。悪いところは一つも無いのに、「真新しい車が浮いている」と感じてしまうような男だった。しかしどうやらその男は、わたしを≪愛≫しているようだった。それが何とも言えない居心地の悪さを生み出した。
時々、不安に襲われた。このままでは男のとてつもない≪愛≫に飲まれてしまうのではないかと。頭からすっぽりと包み込まれて呼吸ができなくなるのではないかと。この気持ちはつまるところ、わたしはまだそこまで男のことを≪愛≫していない、という証明だった。
ある日、男がいつものように銀色の車でわたしを迎えに来た。その頃には男の送り迎えは日常的なことになっていて、わたしは当然のように助手席に座った。けれどその日、男はいつもと違って、行き先も告げずに走り出した。
昼間の首都高速は空いていた。車内にはアンニュイな声のミュージシャンの歌声が流れていた。ボコッとした道路の出っ張りにひっかかって車が浮くたびに、アコースティックギターのリズムとわたしの体が同期していく。うららかな春の日だった———。
◇
どこかわからない場所で一人、わたしはくるくると回っている。体が揺れるたびに、視界のはじに白いワンピースの裾が見えた。「あれ?」と、わたしは気がついた。それは少女の頃、シンガポールのホテルに忘れていったドレスだった。「どうしてこんなところに?」ふしぎにおもって右耳に手をやると、赤いイヤリングをしていた。それはニューヨークで片耳だけ落としたイヤリングだった。ふと、左手に重さを感じてうつむくと、ミッフィーを握っていた。子どもの頃、遊園地で落としたリュックサックになるぬいぐるみだった。
驚いて体中をさわると、いつのまにか、いつか・どこかで落とした、大切な宝物が身についていた。
「なんだ、失くしたものなんて一つも無かったんだ」
いつのまにかあたりは生成りの色をしたあたたかな空間になっていた。遠くから、かすかな香りがする。ほのかに青い、小さな花の香り———。
がくんと銀色の車が揺れて、わたしはハッと目を覚ました。眠っていた? いつのまにか? 口元によだれがついている。起こった出来事以上に、わたしは驚愕していた。
(わたし、とんでもなく安心して眠っていた?)
出てきた言葉にハッとする。安心———それは長い間感じたことのない感情だった。
これまでわたしにとって「眠り」とは、怠惰への恥ずかしさと、喪失への恐怖がまざったものだった。わたしをわたしにさせる世界、壊れやすい宝物、それを見張る門番はわたし自身しかいなかった。だから目を閉じるわけにはいかなかった。けれど意志に反して、毎朝気絶するように意識を失い、短い時間で目が覚める自分がいる。コントロール不可能な身体を持ったわたしは怠惰な人間である気がした。眠りこそ、わたしにとってもっとも居心地の悪いものだった。
なのに今、わたしは安心して眠っていた———?
ふと視線を感じると、男がこちらを見ていた。するとなんだか、泉の湧き出る音が聞こえてきた。最初はこぽりと小さな湧き立ちだったのが、次第にこんこんと激しくなり、いつのまにか辺り一面がきよらかな湖になってしまったようだ。わたしはどうかしている。おさえきれないぐらい動揺している。体の震えをごまかすみたいに銀色の車体が揺れたとき、カーステレオから歌声が流れ出した。
「神様ほんの少しだけ 絵にかいたような幸せを わけてもらうその日まで どうか涙をためておいて」
その時、わかった気がした。≪愛≫とは「安心を与えること」だ———。そして、安心とドキドキは両立するのだ。
「愛されたい」と強く願い、それを逃すたびにのたうちまわり、相手を追いかけまわす……。そんな恋愛をしてきた。彼らは確かに胸をドキドキさせてくれたが、それは締め付けるような痛みをともなうものだった。そんな男女関係しか知らなかったから、わたしは痛みこそが≪愛すること≫だと勘違いしていたのだ。だから目の前の男が、ただただわたしのために何かをするのが嬉しいという態度を取るたびに居心地が悪かった。その様子がわたしの知ってる≪愛≫に結びつかなかったから。
しかし冷静に考えたら、安心感を得られなかったからこそ、わたしはかつての恋人たちを追いかけたのだろう。彼らはわたしを不安にさせ、不安は心に穴を開けた。彼らに愛されれば、その穴は埋まるんじゃないか。そう期待して追いかけた。けれど傷をつける人間が、傷を癒すような能力を持っているかというと、それはおそらくノーなのだ。
そしてもう一つわかったことがある。≪幸せ≫とは、心が満たされて初めて感じられる知覚だ。ハンドルをにぎる男は、いつでもわたしを安心させてくれていた。愛されていると確信させてくれた。それでいて今、わたしは胸を高鳴らせている。わたしは初めて、彼の顔を見た。君って、そういう顔をしていたのね。
いつのまにか、皇居のお堀へ差し掛かった車は千鳥ヶ淵を渡っている。青いボートに恋人たちが乗って浮かんでいる。不安な気持ちだけが恋じゃない。わたしは今、恋をしている。
「眠ってごめんね」そう言うと、「嬉しかった」と君は言った。首都高速に桜が舞っていた。
その後、何回かわたしたちは千鳥ヶ淵を渡った。桜の花が散り、水面が茂った緑色になる季節まで。わたしはいつも彼の車で眠った。それは短い春の恋だった。ありきたりな若い男女の物語だった。
あれから何年たったろう。わたしはタクシーの中で足を組み替える。それなりに大人になり、繊細な感受性で夜の眠りが邪魔されることも無くなった。懐かしく思いながら窓の外を眺めていると、運転手があわせたFMラジオから歌が流れてきた。あの歌だった。
「神様ほんの少しだけ 絵にかいたような幸せを わけてもらうその日まで どうか涙をためておいて」
パーソナリティは、この曲を歌っているのはくるりというバンドで、リリースは2011年、離れ離れになった幼い兄弟が再開する映画の主題歌だと教えてくれた。タイトルは『奇跡』だった———。
今ならわかる。わたしが君の車で眠れたのは、目を閉じている間、君がわたしを見つめていてくれたからだ。わたしをわたしにさせる世界、壊れやすい宝物。それを見張る門番をほんの一瞬、君が肩代わりしてくれていた。銀色の車はわたしのシェルターだった。
まちがいなく、奇跡だったと思う。短い季節。誰かを心底信頼し、安心してこの身を預けた日々。わたしの世界を、君が守ってくれていた。
黒い車が千鳥ヶ淵を渡る。あの日と同じように、堀には恋人たちがボートにのって浮かんでいる。
もしもこの国を動かすような人たちが見たら、わたしも、彼も、あの恋人たちも、特別なところは何も無いように見えるだろう。有象無象の集団に過ぎないと。けれどそんなありきたりな要素が、無数に組み合わさることで、≪わたしたち≫はできている。そんなわたしたちが複雑に絡み合い、相互に作用することで、この≪世界≫はできている。
これはまぎれもない真実だ。どんな大災害が起こっても、わたし自身が目を閉じたとしても、決して失われることはない真実だ。ましてや、あなたたちが「取るに足らない」と軽んじたとしても、必ず存在し続ける。たった一人のかけがえのないわたしは此処にいる。そんなわたしたちの集体こそが≪世界≫なのだ。いい加減、目を閉じるのはやめろ。
首都高速に桜がふりしきっている。来年も同じ景色を観れるようにとわたしは祈る。祈りとは決して受動的なものではなく、未来を信じて、言葉を紡ぐことである。
Text/葭本未織
初出:2020.04.16