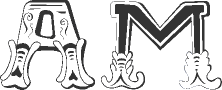「他人のジャッジ」なんていらない。私がどう感じたかが事実だ/葭本未織
永遠の森の100年のふたり
君の手が音楽を奏でている。ジリジリ、静寂、そしてカシャリ。
シャッターを切る音が思いのほか響いて、人のいない参道でわたしの鼓動だけが大きかった。ごまかすみたいにヒールを鳴らして駆け寄ったら「何が撮れたか、まだわかんないよ」と、君は笑った。インスタントカメラに液晶が無いことぐらいお互い知っていた。ひさしぶりのじゃれあいだった。半年ぶりに来た東京は人が少なく、記憶の中の風景とはまるで違う。だけど≪君≫だけは変わらなかった。
君のことをなんて説明しようか、いつも迷う。本当によく笑う人。すらりと伸びた指が美しい人。大学生活の終わりに知り合って、卒業してから仲良くなった人。でも、こんな言葉じゃ、まるで説明しきれない。「意味がわからない関係だ」「その年で友達以上恋人未満なんて未来が無いぞ」と、周囲にはよくからかわれた。
出会って5年目の冬が来ていた。明治神宮は静かに青い。100年前、このあたりは人の住まない荒野だった。何もない荒れ野に≪永遠の森≫を創る。そう決意して造られた鎮守の森は、今や巨木がそびえたち、時には古木が横たわる。その中をわたしたちは歩いていた。敷き詰められた砂利を鳴らすうちに、異なる速度のふたりの歩調が次第にシンクロしていって———ぴたりと重なった時、わたし、吐息が出た。
100年ほどは長くなく、それでいて決して短くない時間が、わたしたちにもある。
◇
泣いてはいけない、と自分を縛りつけていた時期があった。わたしたちが若く、未熟で、トゲだらけの若者だった頃。
当時わたしは、やらかしたミスが人間関係のトラブルにつながって、孤立無援になっていた。ぎすぎすした空気のままプロジェクトは終わり、その日偶然君に会ったら、両目から涙が止まらなくなった。びっくりする君を見て「しまった」と焦り、わたしは矢継ぎ早に言った。
「悲しいんじゃない!一緒に仕事をする仲間に、あんな態度を取られて悔しいんだ!」 それはまちがいなく言い訳だった。プロジェクトメンバーの態度にわたしは傷ついていた。だけどその傷を認めるわけにはいかなかった。一つの傷を認めるということは、これまでにつけられたすべての傷とすべての痛みを≪感じはじめる≫ということだったから———。
「どんなに理不尽なことをされても泣いてはいけない。なぜなら泣けば最後、どれだけ正しいことを言っていても、憐れみを欲しがる目立ちたがり屋の嘘つきだとレッテルを貼られる。だから涙を流すな。ましてや怒るな。他人にとやかく言う前に、自分を変えろ。何事にも傷つかないタフな強さを持て。それが大人だ。自分の感情をあらわにするなんて、幼稚な人間のすることだ!」
と、何度も自分に言い聞かせた。プロジェクトを成功させるために。けれど今、人の行き交う冬の街で、わたしは崩れそうだった。ひとつひとつの≪痛み≫を無視したツケが、体中に回っていた。
(だけど「はい、全部が痛いんです」と認めたら? 痛みを感じはじめたら? わたしは壊れて、二度と立ち上がれなくなってしまう! だから泣き止まないと。何事もなかったかのように振る舞わないと。)
そう思うのに、涙が止まらない。
すると突然、正面から、がしっと両肩を掴まれた。
「大丈夫! 今うまくいかなくても大丈夫! 世の中は広くて、人間はいっぱいいる。続けさえすれば絶対、うまくやっていける人と出会える!」
その瞬間、一筋の光が射した。君の瞳の中にわたしがいた。顔が歪んでいる。痛そうだ。そうわかるやいなや、じっとりした≪痛み≫がものすごいスピードで心を襲いはじめた。けれど、わたしは立っていた。崩れ落ちることもなく、2本の足でしっかりと。
「なあんだ、痛いって感じても、大丈夫なんだね」
と、安堵したら、力が抜けて、君が支えてくれた。わたしは幸せだった。もう自分を縛らなくていい。わたしが感じた気持ち、全部認めてあげていい———。 頭は不思議と冴えていて、これからの行く先が見えていた。
その後、わたしはプロジェクトメンバーと縁を切った。するとより良い出会いに恵まれた。それをうまく繰り返すにつれて、「仕事というのは、自分の考えを伝え、ネゴシエイト(交渉)することなのだ」と学んだ。たくさん失敗はしたけど、そのたびに君は同じように励ましてくれた。この数年間、君がいたから、わたしは前を向いて歩き続けることができた。
突然、君はわたしにカメラを差し出した。
「撮って」
そう言うやいなや、返事も聞かずにジリジリと巻き上げダイヤルを回しはじめる。
「え?」
「せっかくだから。撮ってよ」
「でも、わかんなくなっちゃった」
「わかんないことないでしょ。ここをこうして、シャッター押すだけだよ」
わたしは渋った。ファインダーを覗いたら、君との関係に≪名前≫をつけなくちゃいけない気がしたから———。
かつて、わたしたちは「意味が分からない関係だ」と周囲に呆れられた。「友達以上恋人未満なんて、いい年して幼稚だな」とありふれた言葉でからかわれた。それが脅しみたいにわたしを震えさせてる。呪いみたいに縛ってる。
確かにね、わたしたちは全然意味がわからない。あんな感動的な一幕を演じたわりに、その後100回ぐらいお互いのことを刺した。二度と会わないみたいに話さなかった時期もあるし、きょうだいみたいにくっついていた時期もあった。お互いに傷つけあったり離れたり。でも、それじゃダメ? 誰かにわかりやすい≪ふたり≫じゃなきゃ、≪ふたり≫でいちゃダメなの?
ジリジリという音が聞こえる。巻き上げダイヤルを回す音。同じ音色がわたしの胸からも聞こえてくる。そんな気持ちをちっとも知らずに、君は「撮って」と何度もせがむ。ついにわたしは根負けして、カメラを取ってファインダーを覗いた。
その瞬間———風が吹いた。鬱蒼と茂る葉と葉の間から光が射して、君の顔をまだらに照らす。小さな四角の枠の中に、一つ、屈託ない笑顔がある。
「きれい」
口に出した言葉が胸をキュンと締め付けて「痛かったんだ」とわたしは気づく。心無いセリフで、大切な君との関係をからかわれて、わたし傷ついていたんだな。気持ちが言葉とようやく出会えた。痛みをじんわり感じながら、驚くほど軽く、シャッターは切られた。
◇
現像した写真を見て思わず声が出た。 「え、真っ暗なんやけど?!」 「写ルンです、曇りに弱いねん」
ここは関西の片田舎、なじみの写真屋のおじさんが言った。刷り上がったばかりのL伴は、ついた指紋がはっきり見えるぐらい真っ暗だ。本当ならここには一週間前の東京と、≪君≫が写っているはずだった。
「データ化しよか、それなら調整で多少見えるかも」
おじさんはそう言って、奥に引っ込んだ。気にさせたかなと申し訳なく思いながら、わたしは手元を見つめた。わたしの目に見えたものが、写真にならずに暗闇になった。誰とも共有できなくなった。だけど、気持ちは晴れやかだった。これでいい。いや、これがいい。わたしたちの関係も、わたしの気持ちも。
若く、未熟で、トゲだらけの若者だった頃。痛みを感じたら自分が崩壊してしまうと思っていた。その理由が今ならわかる。他人から「何を痛がってるの?大げさだなあ」と笑われた過去が、わたしたちのすなおな痛覚を「恥ずべきものだ」と縛りつけている。それどころか「もしもこんなことで傷つくなら、お前は幼稚だ。だから大人の社会からは仲間外れにするぞ」と脅している。その経験が積み重なって、わたしたちには≪痛みを知覚することへの怯え≫が染みついた。だから心にヒビが入っても、見てみぬふりをしようとしてしまう。
だけど痛みは、無視し放置することでは決して治癒しない。痛みは「痛い」と感じて初めて、治療という対処ができるようになる。
それに本来、痛みとは「痛い」と感じた張本人だけが感受できる知覚だ。隣で友人がケガをしても、その肉体的な痛みを本質的には理解できないように、≪心の痛み≫もけして他人には理解できない。つまり、起こった出来事をどう感じるは≪わたし≫が決めることであって、他人が口をはさめるものではない、ということだ。そしてそれは、≪わたし≫と≪誰か≫の関係においても同じだ。
わたしがわたしを癒し、前へ進んでいくこと。そのことに君が力を貸してくれたこと。ふたりが過ごしてきた時間。≪わたしたち≫の関係。それには他人のジャッジなんて、ひとつも必要ないのだ。
改めて写真を見る。わたしたちのこと、他人になんて分かんなくていい。この写真みたいに、意味不明なままでいい。他人を安心させるために、わたしたちは一緒に居たんじゃないんだから。
「できたで!」と帰ってきたおじさんに追加料金を要求されて、わたしは思わずズッコケる。心配させてしまったかと気にしてた時間がもったいない。
写真屋を出て、家路をたどる。頬を撫でる風に春の訪れを感じる。
ねえ君、人からどう見えるかなんて、本当に気にしなくていいんだね。君が気づかせてくれたこと、わたしは何度も見失ってしまうけれど、そのたびにもう一度見つけ出すよ。100年前、何もない荒野に、永遠を信じて森を創った人たちのように。写らなかったあの日の互いの笑顔のように。誰にも見えない未来の景色を、わたしたちだけはずっと見ていようね。
Text/葭本未織
初出:2020.03.27