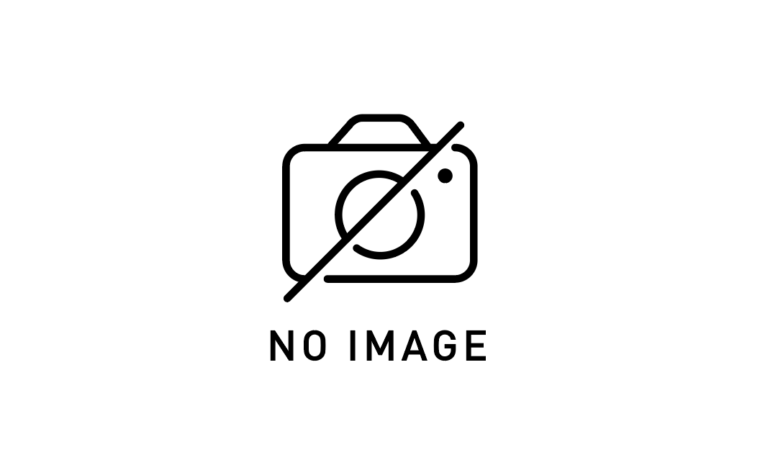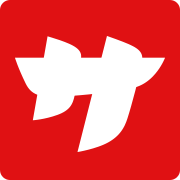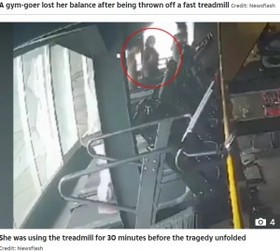「皮剥ぎの刑」が行われた例を5つ紹介! 生きた人間の皮膚を剥ぐ残酷な処刑法
歴史上の怖ろしい処刑法の一つに、生きている人間の皮を剥ぐ「皮剥ぎの刑」がある。メソポタミアのアッシリア人や中米のポポロカ族など数多くの古代文明だけでなく、明代の中国や16世紀のヨーロッパでも、皮剥ぎの刑が行われてきた。現代人からしてみれば残酷としか言いようがない行為だが、罪人に苦痛を与えるためだけでなく、見せしめの意味合いも大きいものとして行われていたという。今回はそんな皮剝ぎの例を5つ紹介し、その残忍さを知ることで、人権尊重の大切さをもう一度思い出したい。
古代アッシリア人の皮剥ぎ
古代アッシリア時代(紀元前800年頃)に作られた石の彫刻には、戦士たちが捕虜の体から皮を剥ぎ取っている様子が描かれている。
アッシリアは世界で最も古い帝国の1つで、現在のイラク北部に位置していたとされる。アッシリア人は、新たな戦闘技術と鉄製の武器を使用して、敵の都市を次々と占領することで版図を広げた。捕虜が拷問されるのは日常茶飯事だった。
アッシリアの皮剥ぎの刑は、考古学NPO「聖書考古学協会」のエリカ・ベリブトレウ氏によって報告された。これによると、アッシリア王のアッシュル・ナツィルパル2世は、服従を拒んだ都市の住人たちの皮を剥ぎ取り、その皮をかけたという。不服従に対する見せしめとして皮剥ぎの刑が行われたと考えられている。
明の初代皇帝による皮剥ぎ
1368~1644年までの約300年間、中国では明王朝が専制政治を行った。洪武帝としても有名な初代皇帝の朱元璋は特に残酷であったとされる。1368年、朱元璋は20万を越える大軍を侵攻させ、元の首都大都を占領して明王朝を樹立した。
朱元璋は、自らを批判する者たちをことごとく死刑にした。謀反を企てたとされる功臣だけでなく、その親戚、友人、仲間をすべて粛清した。約4万人もの命が奪われたともいわれる。処刑された者たちの中には、皮を剥がされて肉を壁に釘付けにされた者もいる。歯向かう者には容赦しないことを示すためだったとされる。
ポポロカ族による皮剥ぎ
現在のメキシコには、アステカ文明が成立する前、ポポロカ族が住んでいた。ポポロカ族は「シペ・トテック」と呼ばれる神を崇拝していた。シペ・トテックは「皮を剥かれた我らが主」を意味する。
シペ・トテックの司祭は、儀式で戦争の捕虜を人身御供としていた。毎年春に40日間かけて行われる儀式では、司祭が色彩豊かな衣装と宝石を身に着けてシペ・トテックに扮し、豊作を願って捕虜の皮膚を剥がし、その皮膚を身にまとったとされる。儀式の様子は、ポポロカ神殿とアステカ神殿の両方に描かれている。
絵画に描かれる皮剥ぎ
皮剥ぎの刑は16世紀まで文化全体で重要な役割を果たし続けた。
イタリア・ルネッサンス期の芸術家ティツィアーノ・ヴェチェッリオは1570~1576年に『マルシュアスの皮剥ぎ』を描いた。この絵には、アポロンとの音楽合戦に敗れた半人半獣の精霊マルシュアスが、罰として生きたまま皮膚を剥がされるという神話のワンシーンが描かれている。
別の絵画『聖バルトロマイの皮剥ぎ』に描かれるは、イエスの十二支と一人であるバルトロマイが、アルメニア王ポリミウスをキリスト教に改宗させた後、生きたまま皮膚を剥がれて殉教した様子である。
民間伝承やおとぎ話で語られる皮剥ぎ
世界中の民間伝承やおとぎ話にも皮剥ぎの物語がある。
スコットランドの民間伝承に登場するセルキー族は、ふだんは海中で生活しているが、陸にあがるときにあざらしの皮を脱いで人間の姿に変わるとされる。 ハンターの男によって皮を盗まれた女セルキーが、男と結婚させられた後、再び皮を見つけて海に逃げる話がある。
イタリアの古い民話「皮を剥がれた老婆」は、森の中に住む2人の未婚の姉妹の物語だ。妹は、妖精を笑わせたお礼として若さと美しさを得て、国王と結婚することになる。これに嫉妬した姉は、妹から「若返るためには自分の皮を剥がなければならない」と言われ、理髪師に頼んで皮を剥いでもらうが、出血多量で死亡する。
アイスランドには、死んだ人間の皮膚から作られたパンツによって金持ちになれるという「死者のパンツ」の話がある。しかし、死者のパンツを作るのは難しい。まず、誰かが死ぬ前にその人から皮膚を使うことの許可を得なければならない。次に、その人が死んだら、遺体を掘り起こし、腰から下の皮膚を剥いでパンツを作る。最後に、そのパンツの陰嚢に、未亡人から盗んだコインと、呪文の書かれた紙を入れておく。一連の作業が終わると、死者のパンツの陰嚢にコインが補充され続けるという。
現在、皮剥ぎの刑は人権侵害とみなされ、すべての国々で違法とされる。しかし、戦争などをきっかけにサディスティックな本性を露呈した者たちが皮剥ぎを行うこともある。
第二次世界大戦中のナチス・ドイツの蛮行として、人間の皮膚からさまざまなものを作ったという逸話が残っている。ブーヘンヴァルト強制収容所の女性看守だったイルゼ・コッホは、収容者の皮膚からランプシェードやブックカバーなどを作ったり、タトゥーのある皮膚を剥いでコレクションしたりしたとされる。また、ナチス親衛隊の医師だったジクムント・ラッシャーも、友人や同僚のために収容者の皮膚でカバンなどを作っていたという。
皮剥ぎの刑の歴史を振り返り、人間の残虐性を直視することが、蛮行を繰り返さないためにも必要なのかもしれない。
参考:「All That’s Interesting」、ほか