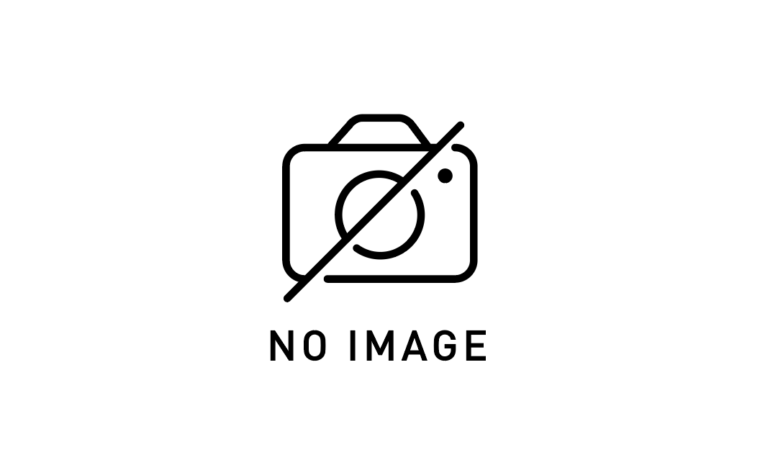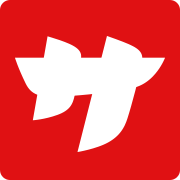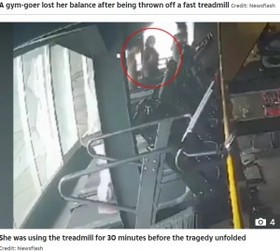元NHKアナ・藤井康生「喋ってくれない力士たち」から話を聞き出す技術
大相撲中継を約40年に渡り担当し、今年1月に定年となった大阪学院大学特任教授で元NHKアナウンサーの藤井康生さん。中継に欠かせないインタビューだが、力士といえば朴訥として寡黙なイメージも強い。40年の思い出話とともに、インタビューで話を引き出すノウハウと心構えを聞いた。
◆喋ってくれない力士たち
――最近では変化しつつありますが、かつては力士はあまり喋らないようなイメージもありました。
藤井康生さん(以下、藤井):私が大相撲担当になったのが昭和59年なのですが、当時はやはり「力士たるもの」というイメージがあるので、「あまり人前でベラベラ喋るな」と指導をする親方もいました。
――なぜ喋らないことが良いとされていたんでしょうか。
藤井:勝った力士にインタビューをしますが、支度部屋のテレビではNHKの大相撲中継が流れているので、その力士に負けた相手が見ているかもしれません。勝った自分は嬉しくても、相手の気持ちを慮るということですね。
――まさに「相撲”道”」ですね。そういった考えを顕著に持っていたのは、どの親方でしたか?
藤井:二子山親方(初代貴ノ花)です。最近、息子の若乃花さん(花田虎上)とよく仕事で一緒になって楽しく話しますが、彼は二子山親方の教えもあり、現役時代は喋ってくれませんでした。同じ二子山部屋の安芸乃島さんも、インタビューで全然喋ってくれず大変でした(笑)。
――安芸乃島関は、インタビューの回数も多かった力士ですね。
藤井:金星(横綱からの勝利)も多かったのでよくインタビューしました。彼はすぐ「覚えてません」って答えるんですよ(笑)。「では、覚えている範囲で教えてください」と振っても「覚えてません」と返ってきたのを思い出しますね(笑)。
◆苦い思い出の優勝インタビュー
――うまくいったインタビューの思い出はありますか?
藤井:ほぼないです(笑)。私がはじめて優勝インタビューを担当したのが、昭和63年の1月場所で、当時は、表彰式の前に支度部屋で優勝力士に話を聞くスタイルでした。旭富士(現:伊勢ケ浜親方)が初優勝した場所で、「放送席、放送席」と呼び出して、質問を始めたんですが、これがまぁ喋らない!(笑)どんな質問をしても「そっすね」ばっかりなんですよ。
周りに新聞記者たちがいるんですが「ちゃんと聞けよ」みたいな雰囲気になって、そのまま終わってしまいました。先輩にもこっぴどく叱られましたよ。
――苦いデビュー戦になりましたね。
藤井:次に優勝インタビューを担当したのが、平成3年1月場所で、優勝は霧島(現:陸奥親方)なんですが、これがまた喋らない(笑)。当時は、大乃国や千代の富士や北勝海など、喋ってくれる力士も優勝していたんですが、なぜか私の担当する場所だけ、喋らない力士が優勝するんですよ。このふたつのインタビューは一生忘れないでしょうね。
◆インタビューに成功はない
――そんな中でどんな手を使って話を引き出したんですか?
藤井:手の使いようはないです。ただ、ストレートに突っ込むほど、さらに喋らなくなることはわかってきました。「今、どんな気持ちですか?」なんて聞いても、見ている人が喜ぶような答えは返ってきません。
――質問はあらかじめ準備しておくんですか?
藤井:若い頃は準備していましたが、それがほぼ使えないとわかって、準備はしなくなりましたね。引き技のようなつまらない相撲で勝ってインタビュールームに来る場合もありますから。
――さすがに「つまらない勝ち方でしたね」とは言えませんよね(笑)
藤井:そういうときは「だいぶ考えて立ち合いましたか?」など、聞きますね。引き技で勝っても、考えた上の作戦ということもあって、本人が「つまらない勝ち方」だと思っているかはわかりませんので。
――力士がどう思っているか、感じ取ることが大事になりますね?
藤井:現役だと遠藤関など、感情をあまり出さない力士の場合はそれを読み取るのが大変です。逆に玉鷲関はわかりやすい。引いて勝った相撲の後に「やっちゃったよ~」と言いながら入って来ることもありました(笑)。そういう場合は「やっちゃいましたね」とインタビューを始めて、「考えて取り組んだのか」などを深掘りしていきます。
――確かにそれだと、準備は意味をなさなくなりますね。
藤井:「相手の答えに反応しながら質問をする」のが大事です。前もって用意したものを質問するだけでは、会話になりません。力士が「立ち合い迷ったんですが」と言ったら「どんな風に迷ったんですか?」と会話を膨らませていくんです。これは、若いアナウンサーにも教えています。
◆どうせ「娯楽」なんだから
――長年、インタビューをされてきて、ポリシーはありますか?
藤井:子供の頃に大好きだった相撲が、仕事になってからは楽しめなくなっていました。しかしあるとき、先輩に「難しいことはいいから、あなたも楽しみなさい。見る人にとっては、どうせ娯楽なんだから」と言われたんですよ。たしかに見る人は、技術的どうこうより「勝った!やったー!」と思う人が大半なんですよ。大相撲に限らずスポーツはそうですね。
先輩にその言葉をかけてもらってからは、緊張感は持ちながらも、インタビューでは気の利いたことを引き出すように考えられるようになって、向き合い方が変わりましたね。
――相撲を大好きなインタビュアーが、その気持ちで質問してくれれば、それがファンの聞きたいということですね。インタビューでよく聞く言葉ではなく、その人なりの言葉をを引き出したいという感覚ですね。
藤井:でも出ちゃうんです。どんな質問をしても、力士たちは「一番一番やるだけです」で逃れようとします(笑)。終盤に「優勝争いの先頭にいますが」と振っても「一番一番」なんですよ。
――そこを、そんな風に切り込むんですか?
藤井:こっちは「そんなことはないだろ」と思いながら聞くので、力士との関係性によってはそのまま「さすがに意識するでしょう?」とか「せっかくこのチャンスだから意識してもいいんじゃないですか?」なんて切り込むこともあります。
――かなり力士の懐に飛び込む言い回しですね。
藤井:視聴者は「失礼な奴だな」と思うかもしれませんが、力士との関係性も踏まえて、自分が悪者になるということはやります。
◆「我慢」が引き出した歴史に残る名言
――相撲とは離れますが、有森裕子さんがアトランタ五輪で銅メダルを取って「名言」を残しました。その時のインタビュアーは藤井さんだったんですよね。
藤井:インタビューで有森さんは「前のバルセロナ五輪で銀メダルを獲得したんですが、自分自身『勝負にいけなかった』という反省を持っていた。そこからアトランタに臨んで、結果は銅メダルだったけれども、『勝負にいけた』という実感があったので納得している」といった話をしてくれていました。インタビューが進んでいくと、彼女の内側から感情が込み上げて来るような雰囲気があって、涙で言葉が途切れるようになってきました。そして、一瞬黙ったんです。
――短いインタビュー時間ということもあり、次の質問をしたくなりますね。
藤井:でも私はそこで待ったんです。すると彼女から「初めて自分で自分を褒めたいと思います」という言葉が出てきたんですよね。
――次の質問をしていたら出てこなかった言葉ですね。
藤井:放送中に黙るのは怖いんですが、我慢も大事です。
◆自分の範囲の外にいる人といかに喋るか
――普段から心がけていることはありますか?
藤井:日常の会話にも意識を向けることです。今こうやって、ツバキングさん(筆者)と話すときも、会話を意識します。インタビューも会話ですからね。
――放送席での解説者とのやりとりも会話ですね。
藤井:北の富士勝昭さんという解説者がいます。大変な横綱で、相撲解説者としても歴史上一番すごい人だと思います。若いアナウンサーは、そんな方と放送席で並ぶと、年齢も知識の量も桁違いなので、萎縮するんですよ。
――そこを乗り越えて、いい解説を引き出さなくてはいけない。
藤井:北の富士さんは最初「なんでも聞いてくれればいいんだよ」なんて言ってくれます。でも、放送中に若いアナウンサーが解説を求めると「あ、今見てなかったから、舞の海に聞いて」なんて、はぐらかしたりするんですよ(笑)。ちょっと試しているのかもしれませんね。
――中継でよく見かけますね(笑)
藤井:でもそこを乗り越えたら、経験も知識も豊富な人なので、勝手に面白くしてくれるんです。それができるようになるために、普段から年齢の離れた相手との会話を意識してやることも大事ですね。上司でもタイミングによってはツッコミを入れてみたり。
――今、SNS時代は趣味や年齢の近い人ばかりで集まりがち、年齢も離れて趣味も違う人と会話をするのは大事ですね。
藤井:その通りです。自分の範囲の外にいる人といかに喋るかです。それができれば人間として大きく広がって、会話の豊かさが変わってきますね。
なかなか話をしてくれない相手から、気持ちを引き出すインタビューに、成功体験はないと話す藤井さん。しかし、その一言一言からは、私たちが仕事やプライベートでのコミュニケーションで、人から話を引き出す場面で意識できそうな心がけが詰まっていた。<取材・文/Mr.tsubaking>
【Mr.tsubaking】
Boogie the マッハモータースのドラマーとして、NHK「大!天才てれびくん」の主題歌を担当し、サエキけんぞうや野宮真貴らのバックバンドも務める。またBS朝日「世界の名画」をはじめ、放送作家としても活動し、Webサイト「世界の美術館」での美術コラムやニュースサイト「TABLO」での珍スポット連載を執筆。そのほか、旅行会社などで仏像解説も。