Netflix「新聞記者」と小山田圭吾さん騒動との共通点 取材者のモラルはどこへ行った
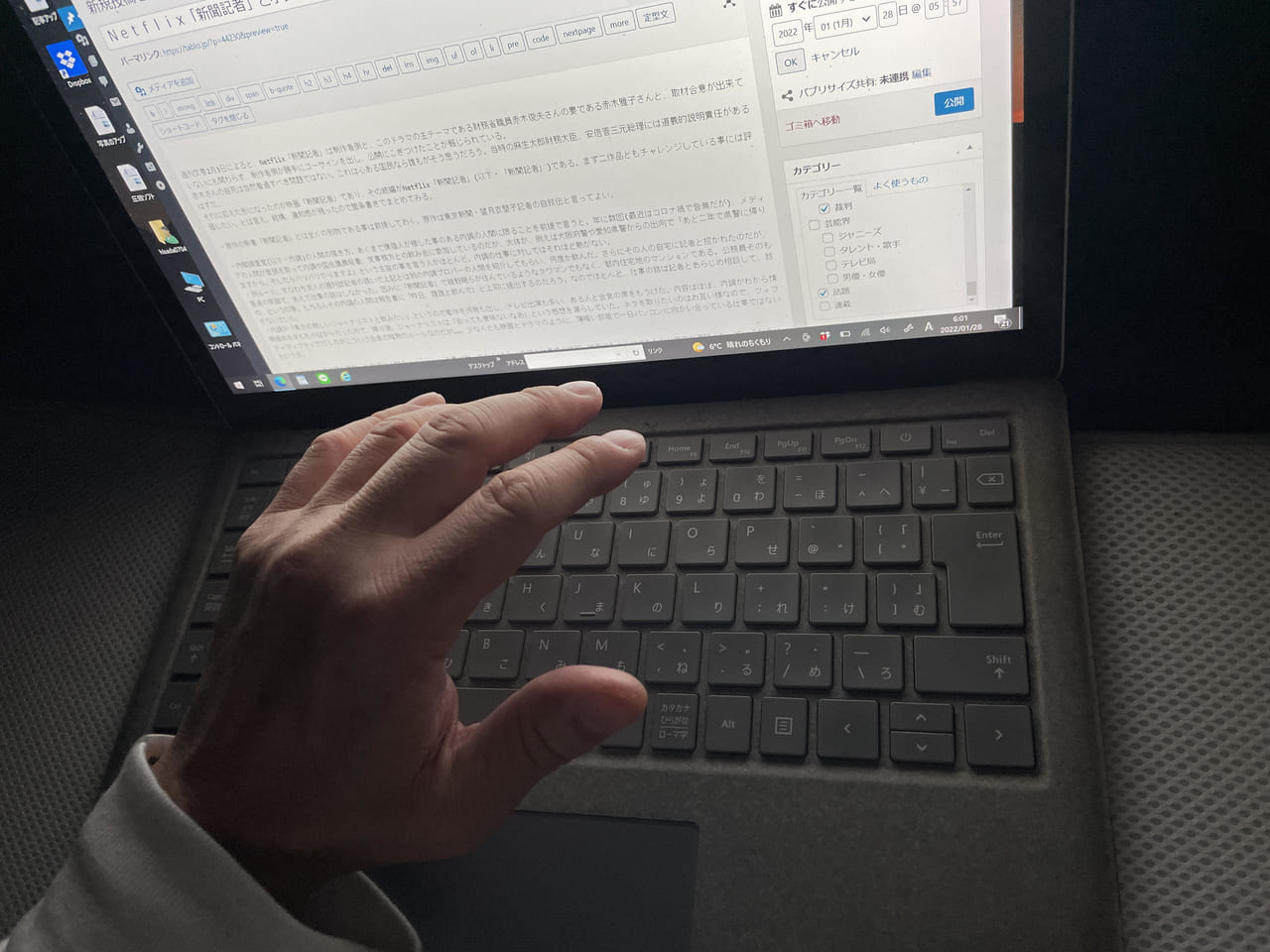
週刊文春2月3日によると、Netflix「新聞記者」は制作者側と、このドラマの主テーマである財務省職員赤木俊夫さんの妻である赤木雅子さんと、取材合意が出来ていないにも関わらず、制作者側が勝手にゴーサインを出し、公開にこぎつけたことが報じられている。
赤木さんの自死は当然看過すべき問題ではない。これは心ある国民なら誰もがそう思うだろう。当時の麻生太郎財務大臣、安倍晋三元総理には道義的説明責任があるはずだ。
それに応えた形になったのが映画「新聞記者」であり、その続編がNetflix「新聞記者」(以下・「新聞記者」)である。まず二作品ともチャレンジしている事には評価したい。とは言え、結構、違和感が残ったので箇条書きでまとめてみる。
●原作の新書「新聞記者」とは全くの別物である事は前提しておく。原作は東京新聞・望月衣塑子記者の自叙伝と言ってよい。
●内閣調査室(以下・内調)の人間の描き方。あくまで僕個人が接した事のある内調の人間に限ることを前提で言う。年に数回(最近はコロナ禍で皆無だが)、メディアの人間が音頭を取った内調や国会議員秘書、党事務方との飲み会に参加しているのだが、大体が、例えば大阪府警や愛知県警からの出向で「あと二年で県警に帰りますから。そしたらバリバリやりますよ」という主旨の事を言う人がほとんど。内調の仕事に対してはそれほど熱がない。
●別ルート、すなわち友人の週刊誌記者の誘いで上記とは別の内調の人間を紹介してもらい、何度か飲んだ。さらにその人の自宅に記者と招かれたのだが、普通の家庭で、あえて仕事の話はしなかった。因みに「新聞記者」での登場人物が住んでいるようなタワマンでもなく、都内住宅地のマンションである。公務員そのもの、という印象。もちろんその内調の人間は報告書に「昨日、誰誰と飲んで」と上司に提出するのだろう。なので記者とあらじめ相談して、仕事の事は話さないでいた。
●内調が「貴方の親しいジャーナリストと飲みたい」というので著作を何冊か出し、テレビ出演も多い、ある人と会食の席をもうけた。内容はほぼ、内調がわから情報提供を求むものばかりだったので、帰り道、ジャーナリストは「会っても意味ないなあ」という感想を漏らしていた。ネタを取りたいのはお互い様なので、フィフティフィフティで行くのがこういう会食の暗黙のルールなのだが……。少なくとも映画・ドラマのように、薄暗い部屋で一日パソコンに向かい合っている仕事ではないという点。
●上記はあくまで僕が接触した内調の人間のイメージという事は断っておく(あと、内調の仕事場の描写。映画でもドラマでもかなり室内が薄暗くなっているが大ヒットアメリカドラマ「24」あたりの影響だろうか。歩いていると部屋が暗すぎてつまづきそうである)。
内調に関して、リアリティに欠けるというイメージを「新聞記者」に抱いたメディアの人間は実は多い。内調と言うとCIAやKGBのようなイメージを持つ人が多いかも知れないが、僕の認識だと公安警察がそちらに類すると思う。ではなくて、僕個人の内調のイメージはザ・公務員だ。
それでも映画「新聞記者」についてリベラル(僕と同行した記者もリベラル)のメディアが何も言わないのは、政権批判がテーマにあったからだろう。細かい描写については目をつむっておけ、という訳だ。それは分かる。なので映画「新聞記者」については意欲作だと僕は思っている。
問題はネットフリックス「新聞記者」だ。週刊文春の記事が真実性に基づいているあるいは真実に相当たる理由がある、という前提での本稿だ。
要約すると財務局赤木俊夫さんの妻雅子さんに、週刊文春記事(赤木さんの遺書)が出た後、映画の原作者である東京新聞望月記者から手紙が届いた。内容は、記事を読んで涙が止まらない。それでネットフリックスで「新聞記者」を制作中の河村光庸プロデューサーの手紙を同封している。内容は協力をお願いしたいとの事。が、ZOOMで会話した時の河村プロデューサーの女優らを呼び捨てにしたりする上から目線(記事にはそう書いてはいないが)と赤木さんを診察した精神科医を批判する事に訝しい思いをしたので断った。が、望月記者は粘り、彼女とだけはつながった。
というような関係性である。望月記者には自宅取材、家族との写真、遺書などを提供(当然貸し出し)。そして、いったん雅子さんが「新聞記者」の協力を拒んだにも関わらず、「窓口」の望月記者とやり取りをしていた最中、Netflixで「新聞記者」が公開される(正確には小泉今日子と米倉涼子が共演か、という記事)事を知る。驚いた雅子さんは望月記者に連絡を取るが「子どもがいるという設定なのでフィクション」ということを言われる。結局、うやむやのまま公開に踏み切るのだが、小泉今日子が赤木さんの了解を取っていない事を知り、役を降りるという事態になっていた―ー。
「フィクションなんだから雅子さんの了解を得なくてもいい」
結局河村氏は悪い意味で、凄い開き直りをして公開してしまう。映画では原作者との間でトラブルが起こる事も間々ある。そういう場合でも「この話は実話に基づきます」とか「Based on a TrueStory」という字幕が映画の最初か最後に入る。つまり、実在の人物の家族の了解を得るのは、基本である。演出上のトラブルとは別もの。
その基本をすっ飛ばして「新聞記者」は公開された。雅子さんの心を踏みにじった麻生太郎大臣(当時)の心ない言葉があった。それと「フィクションを言い訳にして公開しよう」という河村プロデューサーの精神構造は実は通底しているのではないか。分かりやすく言うと河村さんや望月記者に麻生大臣を批判出来る資格があるのか、と言う事だ。雅子さんを傷つけた、という行為を両者はしているのだから。
『翔んで埼玉』でアカデミー受賞の武内英樹監督が待遇不満でフジテレビを退社か 「みんなNetFlixに行ってしまう」(映画関係者) | TABLO
「新聞記者」のヒットで一躍寵児となった望月記者と河村プロデューサー。週刊文春の記事を読む限り、「新聞記者」のメインテーマである「赤木さん事件」(とここではあえて呼ぶ)の取材協力者の妻・雅子さんの協力がなければ成り立たなかったドラマだ。
取材者と被取材者の関係性について抑えておくとあくまで望月記者は雅子さんに「取材させて頂いている」のである。新聞記者が偉いのではない。当然、テレビ記者が偉いのでもない。「無理を言って家族の写真や遺書の貸出をして頂いている」のである。その人の心を傷つけてどうする。
ここである騒動を思い出した。
ミュージシャン小山田圭吾さん騒動である。
小山田圭吾さん騒動とは過去のイジメ経験を「ロッキンオンジャパン」及び「QuickJAPAN」(以下・QJ)に告白。掲載当時から炎上し、結局、約20年後の東京オリンピック・パラリンピックの開会式の作曲担当者に小山田さんらを起用する事がニュースになり、また炎上。抗議などで小山田さんは謝罪し立場を辞す事になる。
イジメは絶対になくすべきだ。人類が無くさなくてはならないものに、弱者イジメ、差別、戦争があると思っているが、イジメは絶対にいけない。これは大前提だ。
その上で、ここでは記事全文を読んだ「QJ」に限って指摘するが、当時人気絶頂だった小山田圭吾さんに「QJ」はお願いする形で「イジメ体験とイジメられた人の対談」を企画した。対談は実現しなかったので、打合せ段階での小山田さんの話を記事として掲載。
結果、炎上するのだが「週刊文春」の小山田圭吾さんインタビューを始め、小山田さんが当時「QJ」に語った壮絶なイジメはそこまではなかった、という主旨の告白をしている。にもかかわらず、20年にわたって炎上してきた。
問題は、「小山田さんにお願いして」誌面に登場して頂いた「QJ」編集部である。編集人・ページ担当者(当時はライター)・発行人。この三者には小山田さんを守らなければならなかった。なぜなら、著作権(小山田さん)、編集権、発行権の三者で記事及び出版物は成り立っているからだ。それゆえ三者とも責任を取らなければならないはずだが、結局小山田さんだけが罪と罰を受ける形になった(機会があればこの「事件」は備忘録として記事化しておきたい)。
振り返って「新聞記者」である。構図が似ている。完全なトレスは出来ないが、少なくとも「お願いして」雅子さんに協力して頂ている。まずは雅子さんの意志を尊重すべき。小山田圭吾さんの意志を尊重すべきだったように。取材者は被取材者に対して、原則、丁寧にそしてお互いにある程度であっても、信頼関係を築くべき。もちろん不正を糺すといった目的の場合は別だ。しかしこんな記述がある。「望月記者が「報道のため」というから貸し出した写真や画像データ、遺書、音声データなどは一部しか返却されていない」(週刊文春より。ママ)。これが本当なら信頼関係など築けるはずもない。
雅子さんにとって、これから裁判の資料にもなるし思い出の品でもある。その重みは他人には分からないだろう。それを返却しないとは……。取材とは何だろう。取材者の矜持とは何だろう。
権力の不正を糺す時。権力と闘う時。メディア側もなりふり構わず対立していっても良いだろう。しかし、そこに人の死や遺族の思いが絡む場合、記者の前に人としての行動を考えるべきではないか。そう批判するのにはこういった記述が週刊文春にあるからだ。前記の資料、遺書などの返却を雅子さんが望月記者に求めている。すると、
「返してほしくて何度も電話したが応答せず、コールバックもない」(週刊文春より)。
取材者の矜持とは何か。頂いた資料で権力に迫ろうという目的だとしても、取材協力者あっての事だ。
チートでも何でも良い。一時、そういった風潮が吹いたのを感じた事があった。2011年東日本大震災の頃だった。一部文化人が福島原発事故での放射線の恐怖を過剰に煽っていた。しかし煽っていた人たちはもう、表舞台には出ていない。真っ当な取材をしていた人たちは現在も、取材活動を続けている。
僕も福島第一原発の取材をした。記事化されているので名前を出しても良いと思うが、朝日新聞奥山俊宏編集委員と一緒に取材をした作業員のインタビューを掲載した。当たり前だが名前を出さない、職場も出さない、など条件を守りつつ協力者の作業員の立場を2人で尊重し、その作業員の了解のもと、朝日新聞(2021年3月12日夕刊)に掲載。掲載されてから何かのミスがあって、作業員の方からクレームの電話が来るのでは、と緊張したものである。幸いにもなかったが、それほど取材協力者には気を遣うし立場を守らなければいけない。それが取材者としての矜持だと思う。果たして「新聞記者」にはそれがあったのか。
チートはもういらない。真っ当な仕事をする人が残る。(文@久田将義)
福島第一原発事故 10年目で出て来た新事実 「フクシマ・フィフティー」のアナザーストーリー 第1回(インタビュアー│奥山俊宏、久田将義) | TABLO














☆NoB☆Dirty words pollute the soul☆
1/28 15:06
『原作は東京新聞・望月記者の自叙伝』ということで、まったく観る気がしない。