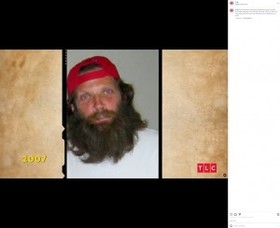「1年以上もご無沙汰だったのに…」ある夜、夫が豹変した驚きの理由
「妻が輝いていることが、僕の喜びです」
令和の東京。妻に理解のある夫が増えている。
この物語の主人公・圭太もそのうちの1人。
・・・が、それは果たして、男の本心なのだろうか?
元来男は、マンスプレイニングをしがちな生き物だ。
高年収の妻を支える夫・圭太を通じて、東京に生きる『価値観アップデート男』の正体を暴いていく。
(マンスプ=マンスプレイニングとは、man+explainで上から目線で女性に説明するの意味)
妻の稼ぎで暮らす主夫
ほとんどの男たちは、僕をバカにする。
先日、大手商社時代の同期が集まって新木場でバーベキューをしたときも、そうだった。
僕が1年前に結婚したことを聞いた男が、酔った勢いで言い放つ。
「圭太って年上のバツイチ女と結婚したの?正気かよ!」
彼は、退職後の僕の生活スタイルを知り、さらに声を張り上げる。
「しかも圭太、専業主夫やってるの?なんだよそれ、ヒモみたいだな!」
たしかに、妻の香織は、僕より年上の36歳で離婚経験者だ。それに、経営者である妻の稼ぎで、僕は暮らしている。
彼に限らず多くの男が、そんな僕を好奇の目で見てくる。
だが、彼らは前時代的だと僕は思っている。価値観をアップデートできていない人間に何を言っても仕方がないから、愛想笑いで返す。
「ははは。主夫も楽しいよ」
僕は藤堂圭太という名前で34年間、男をやってきたから、男の心理をよく理解している。
男たちは戦うことが好きだ。競ってないと生きていけない。だから、僕をバカにして喜んでいるのだ。
女性もマウントを取り合うだろうが、男たちのそれはより具体的だ。
事実、先ほどの愚かな彼は、僕のそばから離れると、別の同期が連れてきた初対面の女性グループに割って入って、ふたたび醜態をさらしている。
「ねー、君たちさ、俺の年収、知りたくない?」
男たちは自分の年収が自分そのものの価値を決めるものだと盲目的に信じ、他の男たちと競い合っている。
僕は、結婚と同時に、男同士の戦いのリングから降りた。
リングから降りて、幸せを噛み締めているこの男の正体とは…
僕は、妻の稼ぎで暮らしてはいるが、収入ゼロではない。そもそも専業主夫でもない。
趣味が高じてイラストレーターとして開業届を出し、しっかりとした収入を得ている。投資も始めたし、実のところ稼ぎは商社に勤めていたときと遜色ない。
ただ妻の収入には到底届かない。実際の金額はわからないが、彼女が収めている税金から逆算すると年収3,000~4,000万円だろう。
妻は忙しい。だから家事を担当することで妻をサポートしている。だって、イラストレーターは家で仕事をするわけだし…それだけのこと。
才色兼備である香織は早稲田大学を卒業後、外資系コンサルティング会社に入り、新卒同期だった男性と付き合ったという。
交際から5年後。結婚を機に彼女は独立し、輸入ファッション雑貨を扱う会社を立ち上げた。
かつては商社で経営戦略部のエースとして将来を期待されていた僕の目から見ても、香織のビジネスセンスは類いまれだ。
彼女の立ち上げた会社はすぐに軌道に乗り、当時の夫の年収をあっという間に超えた。
―― 女は男より稼いではならない。
どうやら男たちの中には、そんな不文律があるらしい。
香織より稼ぎの低くなった前夫は、あからさまに気分を害し、毎日不機嫌な態度で嫌味を言ってくるようになった。
あるとき、香織は我慢の限界を超えた。
「私は、あなたの稼ぎが私より少ないことなんて、これっぽっちも気にしていないの。でも、年収=男の価値だと思ってるあなたってダサい」
夫婦関係は破綻し、香織は前夫と離婚した。
前夫との顛末を聞かされたのは2年前。場所は広尾の『ボッテガ』だ。
僕たちがこれから付き合うかどうかの瀬戸際のデート中、香織はクイズを出してきた。
「面白いのがさ、わたしの年収が夫の年収を上回ってるって知ったとき、彼はどんな行動を取ったと思う?」
「行動?んー。ヒントは?」
「“夜”に関すること」
この夜がどんな意味の夜か、香織の表情で理解した。あのときの彼女は頬が赤かったから酔っていたのだろう。
僕は考える間もなく、すぐに答えが閃いた。
「あ、無理やりベッドに押し倒したとか?」
「えっ…。すごい…正解!」
香織は心底驚いた表情をしていた。
聞けば、同じクイズを色んな人に出したそうだが、ヒントを「夜」とか「ベッド上のこと」とか伝えると、誰もが「レスになったのでは?」と答えたらしい。
「でも圭太くんの答えは、その真逆だった!なんでわかったの?」
妻が自分の年収を超えた途端、男は妻を“女”として見なくなり、レスになる――というのは、現実を認識していない人間の思考だ。
僕は男だから本能的にわかる。
男は、女性を所有し、屈服させたい。
たとえ自分の妻が自分の年収を超えようとも「こいつは俺のモノなんだ」と誇示したい。だから無理やりに押し倒した。
しかし、当時の香織はそれを拒絶した。
「1年以上レスだったのに急に押し倒すなんてねえ。レイプだよね?夫婦間でもレイプって成立するでしょ?」
ワイングラスを片手に、香織はあっけらかんと言った。
「結局、男なんてみんなマンスプしたがる生き物なのよ」
「マンスプ?」
「そう。マンスプレイニング。“man+explain”を合成した言葉で、manは『男』、explainは『説明する』でしょ? 男性は上から目線で女性に説明したがるっていう意味なの。
時代は令和なのに、なんだかんだ言って、男ってみんな女より上にいたいって思ってるのよ。 結婚してそれがよくわかった。というわけで、私、もう再婚はしない。自分を押し殺してまで夫を立てるなんて面倒くさすぎるから」
まだ密集してもよかったころのカウンター席で、鼻筋の通った彼女の横顔を見ながら、僕は恋に落ちた。
「僕は、そんなことないよ。君のこと心から尊敬しているし、活躍している君を応援したい」
◆
僕たちが結婚するまでに、時間はかからなかった。
僕にとっては初婚で、香織にとっては再婚。
趣味のイラストを本業にしたかった僕は、妻の仕事と生活を最大限にサポートすることを申し出た。自ら望んで10年近く勤務した商社を退職した。
香織は、口癖のように告げる言葉がある。
「圭太くんは、私を最大限輝かせてくれる存在」
“別荘”代わりに頻繁に訪れる、夫婦お気に入りの南総のラグジュアリーな温泉宿に泊まると、必ず言う。
シャンパンを飲み、客室バルコニーの露天風呂につかり、東京湾と三浦半島の先に見える富士山を見ながらささやくのだ。
そういう言葉で僕をたたえてくれる妻を誇りに思うし、かくいう僕自身も、妻に褒められる自分が好きだし幸せだ。
苗字、家計、住む場所、住宅ローン、生命保険、そして子ども…。結婚にまつわる、ありとあらゆる“選択肢”を話し合って決めた。ほとんど妻の意見を尊重した。
もちろん、僕は男だ。
僕の中の“男”が、そこらを歩く男たちと同じように「お前、男だろ?それでいいのか?」と問いかけてくることもある。
でも、僕ははっきりと答える。
「それでいい。だって香織を愛しているから。僕は幸せなんだ」
香織に恋した瞬間から今に至るまで、ずっと声を大にして、そう言えた。そう信じていた。
……しかしある日、僕の“幸せの価値観”が揺らぐことになる。
妻が出張中にかかってきた1本の“見知らぬ番号からの着信”で、人生が狂い始める…!?
香織の会社はこれまで、輸入したファッション雑貨を各提携ショップに卸すか、ネット販売することで儲けを出していた。
店舗を構えるにしても、期間限定のポップアップストアぐらいだった。
しかし業績が好調なことを受け、このたび神戸で路面店を出すことになった。
オープンはクリスマス商戦に合わせて11月を予定している。ゆえに夏ぐらいから香織は神戸出張が増えていた。
その日も、僕は羽田空港まで車で香織を送り届け、彼女がラウンジに入るまで見送った。
駐車場に戻ってきたタイミングで、スマホに“070”から始まる番号からの着信が入る。
見知らぬ番号からの着信は、いつもなら出ない。
しかし、少しばかりの解放感もあって電話を取ってしまったのだ。――そう、香織が出張すると家事を休めるので少し気が緩んでしまうのだ。
『もしもし、藤堂さんですか?突然すみません』
電話口から透き通るような声が聞こえてきた。声の主は、僕が通っていた大学の後輩だった。
後輩とはいっても面識はない。現役の大学3年生。これから就職活動が始まるという。
「藤堂さんにOB訪問をさせてほしいんです」
会社勤めをしている間、何度となくOB訪問を受け、そのたびに「これからの若者のため」とばかりに懇切丁寧に対応してきた。
しかし、会社を辞めてからは初めてだ。
電話の主はどうやら、僕がまだ大手商社に勤めていると誤解しているようだ。
「藤堂さんの電話番号は、山村准教授から聞いて…」
山村准教授は、慶應大学時代、僕の「経営戦略とM&A」に関する卒論を担当してくれた恩師だ。ただ勝手に電話番号を教えてもらっては困る。
「申し訳ないですが、僕はもうあの会社を辞めたんですよ」
懇切丁寧に事情を説明したが、電話の相手は聞き入れてはくれない。
「辞められていても構いません。むしろ辞められたほうが、忌憚のない意見を尋ねることができます」
忌憚のない意見を尋ねる――という言葉の使い方はおかしいぞと思いつつ、僕は優しいので学生相手にそんな指摘はしない。
「お願いします。藤堂さんだけが頼りなんです。いろいろ教えてください」
その声色には、電話越しでも伝わってくるほどの情熱があった。
僕は女性の活躍を応援する男だ。
やたらと男だけが活躍する体育会気質の商社で、彼女が活躍する姿を思わず夢想してしまった。彼女の顔すら知らないのに。
「わかりました。今日か明日の昼まででしたら、OB訪問をお受けします」
僕は彼女にそう伝えた。
香織は明日の夜、神戸出張から戻ってくる。それまでの間に、彼女のOB訪問を受けるなら、家事にも影響は出ないだろう。
「ありがとうございます!でしたら今夜お会いしたいです!」
彼女の声が弾んでいた。僕は思わず頬を緩ませる。
「ところで、お名前は何でしたっけ?すいません。最初に名乗ってもらったとき、聞き逃してしまいまして」
「ごめんなさい。清水未久といいます」
刹那、僕はドキリとした。
清水というのは、妻・香織の旧姓だからだ。
もしかして香織の親戚だろうか。それを知っていて、山村准教授は僕の連絡先を彼女に教えたのだろうか。
瞬間的に疑問が湧いたが、同時に「清水という苗字はありふれている。親戚であるわけがない」とも思った。
◆
18時になり、自宅近くの六本木けやき坂にあるカフェで未久と会った。
すぐに、僕は、未久が香織の知り合いかどうかを確認したが、彼女は妻とは親戚でも何でもなかった。
「藤堂さん、ご結婚されていたんですね。お若く見えるので、独身かと思いました」
まだ着慣れていないリクルートスーツに身を包んだ未久は、偏見に満ちたことを言う。
「奥様がもともと『清水さん』なら、わたしのことは『未久』って呼んでください」
僕は、即座に断った。と同時に「この娘、大丈夫なのか?」とも思った。
「じゃ、『未久さん』でお願いします」
こんなOB訪問があるものか、と僕はうんざりする。空港の駐車場で電話に出なければ良かった、とも思った。
▶他にも:「エリートだけど、この男ないな」レストランでデート中、27歳女がガッカリした理由
▶Next:10月10日 日曜更新予定
未久のペースに巻き込まれて迷惑な圭太だったが…。