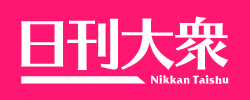室町幕府創設の立役者は女好き!?高師直「元祖のぞき魔」汚名の理由
足利尊氏の執事から室町幕府の事実上の管領職に出世を遂げ、絶大な権勢を振るった高師直。幕府誕生の功労者だった彼は切れ者と評される一方で、極悪非道の悪人、無類の女好きだったともいわれ、評価が真っ二つに分かれる。はたして、どちらがいったい、彼の本当の姿だったのか――。
師直を輩出した高一族の出自を遡ると、天武天皇の皇子である高市皇子に辿り着き、その子孫に当たる高階氏が、やがて「高」と称するようになった。
高氏と足利氏の関係が始まったのは、陸奥鎮守府将軍として活躍した源頼義の時代。源氏(清和源氏)の郎党となった師直の先祖が、下野国足利荘を相続した頼義の孫である源義国の下向に従ったときと考えられ、高氏は師直の曽祖父の時代、足利氏の家政機関だった執事となり、当主の意思を家臣に伝えるため、奉書を発給するようになった。
師直の生年は不詳だが、元弘三年(1333)までには父の師重から執事職を譲られたとみられ、尊氏が同年三月に軍勢とともに鎌倉を発ち、鎌倉幕府を裏切って京の六波羅探題を陥落させ、後醍醐天皇の建武の新政を実現させると、彼をサポート。
尊氏がその後、南朝を興した後醍醐天皇と決裂し、建武五年(1336)に北朝の光明天皇を擁して征夷大将軍に任じられると、足利将軍家が発足し、師直のポストは幕府の執事に格上げされた。
高氏はこうして室町幕府の有力御家人となり、二一か国の守護職を得たことで権勢が盛んとなった。
そんな師直になぜ、悪評が立つようになったのか。
軍記物の『太平記』は彼が一条今出川に豪邸を構え、威勢にまかせて皇族や貴族の娘を囲ったとし、他にも次のようなエピソードを伝えている。
あるとき、侍従の局という女房が師直に取り入るため、唐土(中国)や天竺(インド)の領地と引き換えにしても惜しくないほどの美女(姫宮)がいると彼に囁ささやいた。
その彼女は出雲の守護だった塩冶判官高貞の妻だったが、師直は仲立ちを侍従の局に依頼。
だが、彼女は取り合わず、師直が兼好法師を呼び寄せて送った手紙を開くどころか、庭に捨てる始末。
師直はそれでも諦めきれず、家人に手紙をしたためさせ、再度、侍従の局に届けさせた。
ところが、このときも半ば無視され、彼女に対する思いは募るばかり。
侍従の局は困り果て、師直に女装をさせて塩冶邸に忍び込ませると、彼は彼女の部屋の襖障子奥に身を潜め、湯上り姿を覗き見。
彼女は紅梅の練貫きの衣を纏っただけで、濡れ髪は長く乱れて垂れ下がり、灯火をぼんやりと眺める目つきは妖艶で、その美しさと香の匂いは師直の下心を大層、刺激した。
彼は彼女を奪い取ることを決意し、その夫である高貞が謀叛を企てていると将軍に讒言。高貞は領国に帰って合戦準備をしようとしていたところを討たれ、結局、妻も自害した。
むろん、人妻を奪うために夫を罠にはめて死に追いやったとすれば、まさに極悪非道。
だからだろう、江戸時代には忠臣蔵(赤穂事件)のかたき役である吉良上野介に擬せられ、人形浄瑠璃及び、歌舞伎の演目である『仮名手本忠臣蔵』に足利家の執権として登場。
塩谷判官を恥ずかしめたことから殿中で斬られ、その遺臣である大星由良之助らに後に討たれる。『忠臣蔵』では公儀(江戸幕府)に対する配慮もあり、舞台が南北朝時代に置き換えられ、師直の姿はこうして正真正銘、極悪人として定着するようになった。
だが、実際は御家人らから大きな支持を集めた辣腕の執事といえ、執事執行状の発給はまさに象徴的。
当時、御家人が新たな所領などの恩賞を受ける際、将軍である尊氏の袖判下文が当事者に送られても、その真贋が議論されることも珍しくなかった。
まさに命懸けで合戦に臨み、将軍の下文が届いたところで所領を実効支配できなければ、まったく意味がない。
■太平記の描写によって悪者イメージが定着!?
そこで師直は将軍の意向を受け、当該の御家人が所領を確実に知行できるよう、「沙汰付(武力を伴う強制執行)」することを各地の守護に命令。
御家人はこれがあることで、安心して恩賞を受け取ることができ、だからこそ命懸けで南朝方と戦ったわけで、こうして師直の影響力はさらに高まった。
にもかかわらず、彼は前述のように『太平記』で破廉恥なのぞき魔にされると、悪評はこれだけにとどまらず、皇族や寺社などの伝統的権威を軽視した無学で粗暴な非道徳的な人物というイメージが定着した。
だが、はたして本当に、そう言い切ってしまっていいのだろうか。
師直は禅宗の経典の注釈書を発行し、京都市北区にある真如寺を創建したように仏教を敬った一方、和歌を愛して北朝の勅撰集にも入選しており、無学で粗暴な人物とはどうしても思えない。
ただ、そうした一方で、彼は南朝の正平三年(1348)正月に河内四条畷の合戦で、南朝の楠木正行(楠木正成の遺児)を自刃させ、さらに直後、吉野に侵攻して南朝の皇居を焼き払った。
だからこそ、『太平記』は〈もし王がいなくても叶う道理があれば、木をもって造るか、金をもって鋳るかして、生きている院・国王(上皇・天皇)をば、何方へか、流し捨ててしまえ〉という暴言を彼に吐かせたのではないか。
実際、師直が南朝に強硬な姿勢を貫いたことは確かだろう。
とはいえ、北朝の皇室や寺社までをも否定していたわけではない。内乱期に敵方に強硬な態度を取ることはある意味、当然だ。
ただ、そうした姿勢が当時、負の遺産を一身に背負わされる引き金になったのだろう。『太平記』は尊氏と弟の直義が争った「観応の擾乱」(一三五〇~五二年)で彼を葬り去り、これも彼の印象が悪くなった一因のようだ。
●跡部蛮(あとべ・ばん)1960年、大阪府生まれ。歴史作家、歴史研究家。佛教大学大学院博士後期課程修了。戦国時代を中心に日本史の幅広い時代をテーマに著述活動、講演活動を行う。主な著作に『信長は光秀に「本能寺で家康を討て!」と命じていた』『信長、秀吉、家康「捏造された歴史」』『明智光秀は二人いた!』(いずれも双葉社)などがある。