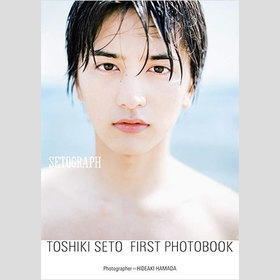14歳年上の人気作家と結婚し“軽井沢ライフ”を楽しむ女。編集者が戦慄した、移住の真実
夏・第6夜「虚弱な男」
「うわ、コレコレ…!文豪の拠点はやっぱ旧軽井沢だな」
東京を出ること2時間。
僕は、新しく担当になった小説家・家永春斗先生の家の前に立った。
緑の木立にちらちらと光が差し、足元を照らしている。ここ旧軽井沢は、別荘地の中でも由緒正しいエリア。
なかでもこの邸宅は、俗世間とは無縁。文豪が住むにふさわしい森の中の静謐な場所だった。
2年前、体調を崩した先生は、結婚と同時に軽井沢の別荘に拠点を移した。
当時、先生は42歳で、彼の熱心なファンだった奥さんは、27歳。編集者の中では、話題になっていた。ただ、僕が先生の担当になったのはほんの1ヶ月前で、これが初めての訪問なのだ。
「こんにちは、杉野さん。東京からようこそ!」
玄関の前の石段を上がりかけたところで、インターホンを押すまでもなく、若い小柄な女性が出迎えてくれた。先生の奥様に違いない。
柔らかな丸みのある体の線は、なんだか安心感がある。色白で目がくりくりしていて、あどけないと言っていいくらいの可愛いらしい女性だった。
― この人が先生の奥様?もうアラサーなはずだけど…どう見ても僕より年下に見えるなあ。
感心しながらもそれを隠し、僕は出版社の使者として、できるだけ礼儀正しく頭を下げた。
「はじめまして、家永先生を担当させていただく杉野亮と申します」
すると、彼女はペコリと頭を下げた。まるで可愛いマスコットみたいだ。
「家永春斗の妻の早穂です。…ようこそいらっしゃいました」
彼女が笑みを深くする。白く柔らかそうな頬に、何かの印のようにくっきりとえくぼが浮かんだ。
編集者・杉野が目撃した作家夫妻の奇妙な行動とは?
驚きの事件
奥様の早穂さんは、ニコニコと僕を奥の応接間に通してくれる。
建物の外観は年季が入っていたが、中は綺麗にリノベーションされ、温かみの感じられるインテリアとともに快適な空間を作り出していた。
広々とした部屋の主役とも言うべき本格的な暖炉が、冬の厳しい寒さと、この部屋で快適に冬ごもりをする様子を想像させた。
「やあ、杉野くん。よく来てくれたね。会うのは初めてだけど、メールでやり取りしているとそんなふうに思えないな」
家永先生は、写真で見たイメージよりもずっと背が高く痩せていて、こう言ってはなんだが意外なほど格好いい男性だった。小柄な早穂さんと並ぶと30cmほども身長差がある。
純文学作家で、正直を言うとこういう人は珍しい。奥さんも美人の部類だし、東京にいたらサイン会を開いたり雑誌に出たりとプロモーション活動をする機会も多かっただろう。編集者としてすこし惜しい感じがした。
「家永先生…!初めまして、杉野亮です。これからどうぞよろしくお願いいたします」
僕は本心からそういうと、先生が大好きだと聞いて気合を入れて選んだウイスキーと、奥様宛ての焼き菓子を手渡した。
「新連載について奇譚のない意見を聞かせてほしい。なんせここに暮らしていてこの体調じゃ、なかなか他の人に会うチャンスもなくてね。来てくれて助かるよ、まあゆっくりして行ってくれ」
◆
「それじゃあ、奥様とは先生の講演会がきっかけで出会ったんですね。ロマンチックだなあ」
新連載の打合せを終え、新幹線を遅らせて早めの夕飯をぜひ、というご夫妻の好意に甘える形で、僕は先生と夕方から食前酒を飲んでいた。早穂さんは、キッチンにいて姿はない。
「そうなんだよ。僕は人見知りだし、若い頃からずっとこの仕事をしていて会社に勤めたこともないから、世間知らずでね。早穂は、やり取りをしてるうちに、秘書みたいなこともしてくれるようになったんだ。若いけれども、本当にしっかりしていて。
それに、結婚する前から毎日三食丁寧に作ってくれていたんだよ。まぁ、ときどき失敗しておかしな味になるけれど。杉野くんも知ってのとおり、僕は数年前から体調を崩しているだろ?彼女がいなかったらどうなっていたことか。公私ともに本当に助けられているよ」
「先生は20年近くずっと売れっ子でお忙しいですから、ご家庭で支えてくれる存在が必要ですよ。このお部屋も本当に居心地が良いし、早穂さんがいると、軽井沢の冬も難なく過ごせますね」
それは本心だった。早穂は若い見た目と裏腹に細かいとことまで気がつくので、この数時間ですっかり感心していた。
「そうなんだよ。僕は気分屋で結婚なんか向いてないし、作家は小さくまとまったらおしまいだと思っているところがあるからね。誰かと暮らすなんて考えていなかったけど、『ある事件』があって、早穂と結婚することを決めたんだ」
家永が早穂と結婚したきっかけとなった、あまりにも奇妙な出来事とは?
独占欲
「ある事件…?」
僕が尋ねようとしたとき、早穂さんが「お夕食の用意ができましたから、ダイニングにどうぞ」と応接間にひょっこり顔を出した。
「ありがとうございます、本当に恐縮です。わわ…すごくいい匂い…!」
先生に促されダイニングルームに行くと、そこには無垢材というのか、美しい木目の食卓に、ところ狭しと美味しそうな料理が並んでいた。
「いつも美味しいものを召し上がっている杉野さんにお出しするのは、恥ずかしいですけれど…。お庭で採れた新鮮なお野菜を使っているものもあるんですよ」
和やかに食事が始まった。
「杉野さん、主人の今度の新作はどういうものになる予定ですか?この人ちっとも教えてくれないから」
ワインを注ぎながら、早穂さんが僕をのぞき込んだ。
熱烈なファンで結婚したくらいだから、先生の作品が気になってしかたないのだろう。
「そうですね、僕はちょっと悲しくて怖いラブストーリーっていうのを期待しているんです。新境地というか」
「怖い話、ですか。ふうん…」
早穂さんは、鴨肉をもぐもぐと咀嚼しながら、ぐるりと目を動かした。
「杉野くん、早穂はこう見えて、なかなか大胆なストーリーを考えつくんだよ。よくできてるから、うっかり影響を受けてしまわないように、この頃では何も相談しないようにしているんだ」
すると早穂さんは、笑いながらもふるふると首を振った。
「でも怖い話はダメ。だいたい、フィクションよりもいつだって現実のほうが怖いのよ、あのことだって…」
「あのこと?」
僕はつい好奇心から、尋ねてしまった。先生が、そうだなというように頷く。
「実はね、杉野くん。僕たちがここに越してきたのも、怖い読者にストーキングされて、すっかり嫌になってしまったという経緯があるんです。
3年前、ちょうど早穂と個人的に付き合いはじめた頃ですが…小説が映画化されて、読者層が一気に広がったでしょう?同時に、熱狂的で奇妙なファンというものも出現しましてね。
妙な電話がかかってきたり、一線を越えたような手紙を寄こしたりするようになったんです」
「え!?先生、それを編集や警察には、相談しなかったんですか?」
初耳だった。僕は驚いて、もう少しで立ち上がるところだった。ファンレターは基本的に出版社経由だ。そのようなものを転送していたとしたら少なからず責任がある。
「もちろん早穂が警察に行ってくれたよ。僕はそういう役所の手続きみたいなことは何もわからないから。でもその程度じゃ動いてくれなくてね…。そうこうしているうちに、ストレスなのか、腹痛やらめまいやらが出てきたんです。
病院に行って検査しても、どこも悪いところはなくて。男性更年期みたいなものかもしれない、とにかく環境を整えたらどうだって医者に勧められて。軽井沢に越してくるタイミングで、彼女と結婚したんだよ」
「その悪質なファンていうのは、特定できたんですか?まさか今も…?」
すると早穂さんは、気味が悪そうに頷いた。3人の会話が途切れると、静寂がくっきりと浮かび上がる。まだ19時すぎのはずだったが、旧軽井沢の森の中、まるで音はしなかった。
「ときどき、東京の家から転送されてくる郵便物には、気味の悪い手紙が定期的に混じっています。家永の創作活動に支障がないように、私が検閲して目に入らないようにしていますけれども…。
なんとかこの軽井沢の家は突き止められないように、私たちは用心してあまり人付き合いもしないようにしてるんです」
僕は言葉を失った。食事会は和やかに続いたけれど、僕はなんだか先生が心配で、あまり楽しめないままおひらきとなった。
◆
「すっかり遅くまでお引止めしてしまって。でもご安心ください、新幹線には必ず間に合うようにお送りしますから」
「いえ、とんでもない。早穂さんが飲んでいらっしゃらないことにもっと早く気がつけば…。タクシーを呼ぶつもりで全く運転のことが頭になくて、申し訳ありませんでした」
僕は恐縮しながら助手席で頭を下げる。旧軽井沢の夜道は車通りも街灯も少なく、早穂さんの運転がとても上手で少しほっとした。
「いいんです、ちょっと除草剤が切れていて…20時までならばお店が開いているから、ついでに寄れるので助かります」
「ああ、あの素敵なガーデニング。早穂さんは本当にスーパー奥様なんですね」
しかし早穂は、それには答えず、ただ不思議な感じに微笑みをたたえていた。
除草剤はガーデニング以外に使い道があるのだろうか。
「…それにしても、先ほどのお話、僕は全然存じ上げず、担当編集として恥ずかしいです。先代の編集も、もっと引き継ぐべきなのに…明日よく話をきいてみます。ストーカーまがいの読者なんて、立派な犯罪ですよ」
「いいんです、私も心配をかけたくなくて最近はどなたにもご相談もしてなくて。それにそのおかげで、家永と軽井沢に二人きりで暮らすことができて、私は案外いいことだなって楽しんでいるんですよ」
楽しい?家永先生はストレスなのか、今も原因不明で体調を崩している。それがなければここに引っ越す必要もなかったのに。
…もしかして早穂さんと結婚して面倒を見てもらう必要もなかったかもしれない。
沈黙が、夜道を進む車内に降りてきた。
「いずれにせよ、杉野さん。熱狂的なファンと、ストーカーの境なんて曖昧なものです。独占欲の差、といったところでしょうか。相手を身も心も自分だけのものにしたいというのは、愛の究極かもしれませんね」
さあ、軽井沢駅につきました、と早穂さんは車を滑らかにターミナル前に滑り込ませた。
「家永を、末永くよろしくお願いいたします。またいつでも、いらしてくださいね」
僕は、何とか笑顔を保ち、深く頭を下げた。
除草剤って、こんな夜に買いにいくほど重要なものなのだろうか?
そしてストーカー被害は果たして本当に警察に届けられているのだろうか。
…いや、そもそも本当に存在しているのだろうか?
一度うまれた恐ろしい想像を、僕は胸の内で持て余しながら、早穂さんの車が去っていくのをじっと見つめていた。
▶前回:港区の“朝活”に現れる30歳・美容外科医。美人で完璧な女の知られざる裏の顔
▶NEXT:7月19日 月曜更新予定
夏・第七夜「初恋の男」ある日知らない番号から、一本の電話。出てみると、10年ぶりの意外なアノ男で…?